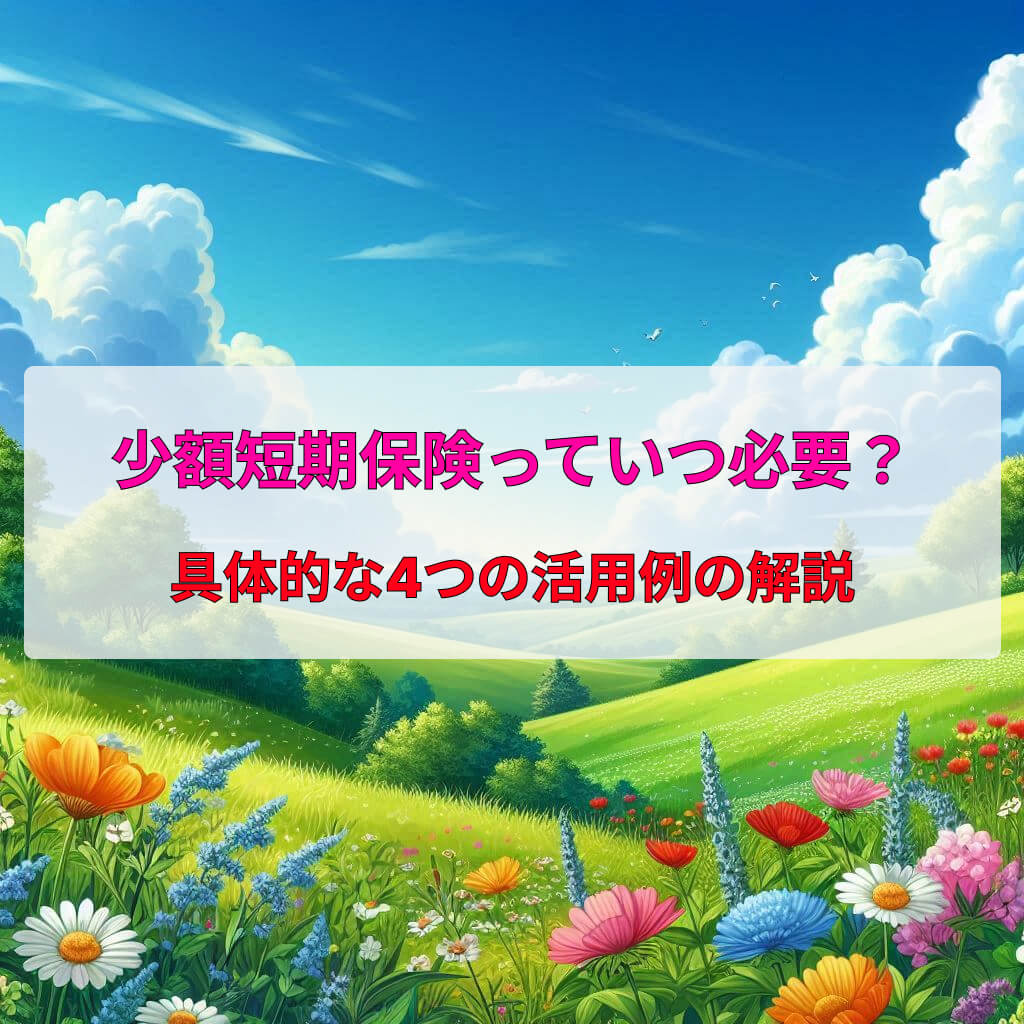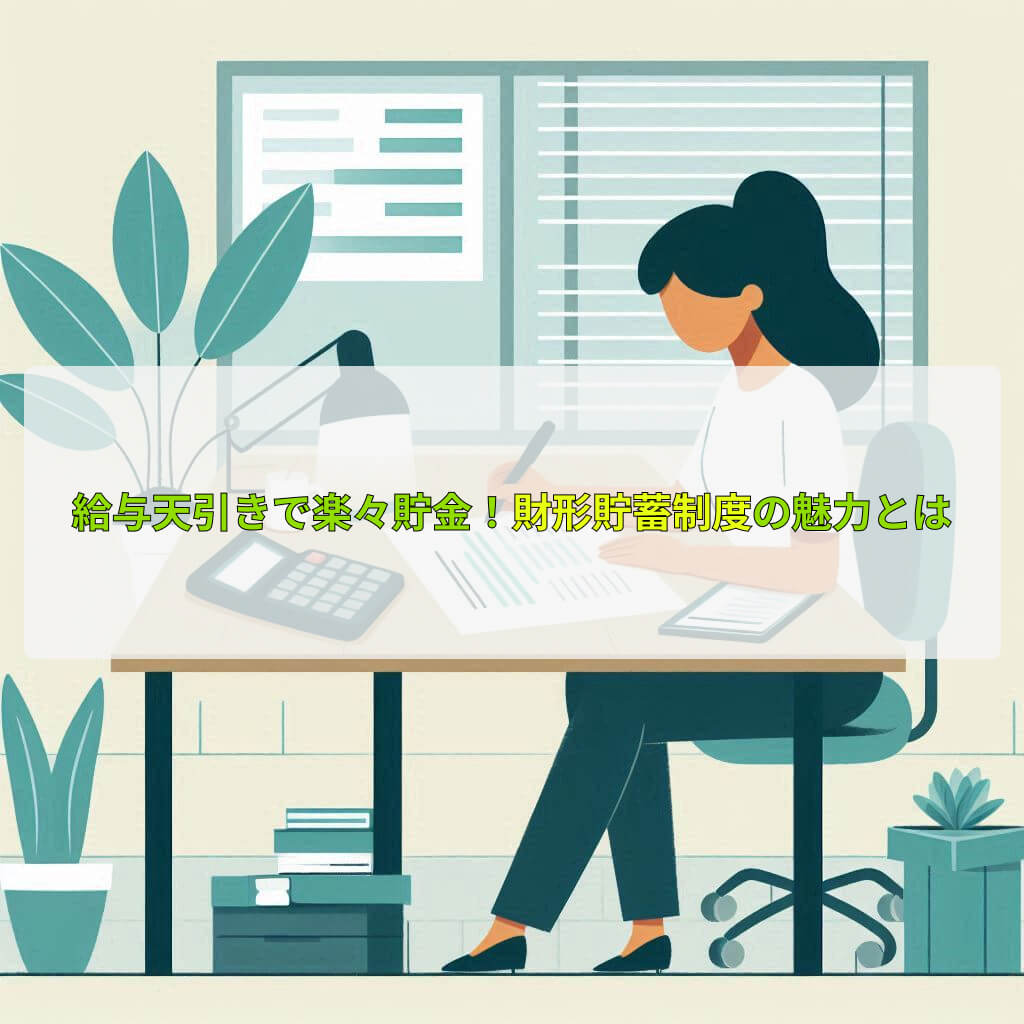学資保険とは、子どもの教育資金を効率的に準備するための手段の一つです。
しかし、学資保険にはメリットだけでなく、注意すべき点もいくつか存在します。
そのため、これから加入を検討する方は、これらをしっかりと把握しておく必要があります。
本記事では、学資保険の役割を詳しく解説し、他の教育資金準備方法との違いや、それぞれのメリット・デメリットについて見ていきます。
この記事で分かること
- 学資保険の概要
- 他の教育資金準備方法の違い
- 学資保険のライフプランニングにおける役割
そもそも学資保険とは?
そもそも、学資保険とはどのような保険なのでしょうか。
まず初めに、学資保険の役割や特徴について見ていきましょう。
学資保険の目的
学資保険は一般的に、将来の教育資金を積み立てるための手段としてよく知られていますが、実は万が一の備えとしての役割も果たします。
学資保険の目的には、大きく分けて以下の2つがあります。
①教育費の積み立て
学資保険を活用することで、教育資金が必要となるタイミングに合わせて進学祝金や満期保険金を受け取ることができます。
②万が一の保障
教育資金の積み立てだけでなく、契約者が死亡や高度障害状態になった場合、保険料が免除され、給付金を受け取れる保障があります。

ちなみに、学資保険は生命保険の一種であり、生命保険料控除の対象となります。
関連コラム
・生命保険料控除のメリットを最大化するためのガイド
学資保険の4つの仕組み(メリットを含む)
学資保険の基本的な仕組みを、以下4つにまとめます。
1. 保険料の支払い
学資保険は、契約者(親や保護者)が一定期間、毎月または年単位で保険料を支払うことで成り立っています。
支払い期間は、子どもが中学・高校・大学に進学する前までが一般的です。
2. 給付金の受け取り
保険期間中、子どもの進学などのタイミングに合わせて、一定の給付金(祝い金や教育資金)を受け取ります。
多くの場合、小学校・中学校・高校・大学の入学時に祝い金が給付されます。
また、契約期間満了時には、満期保険金としてまとまった金額を受け取ることができます。
3. 保障機能
学資保険の特徴として、契約者である親が死亡したり高度障害状態になった場合、それ以降の保険料支払いが免除される仕組みがあります。
この場合でも、契約時に定められた給付金や満期保険金は予定通り支払われます。
4. 貯蓄性
学資保険は貯蓄型の保険です。
保険料を積み立てていくことで、契約期間満了時に満期保険金を受け取りますが、満期保険金の受け取り額は、払込保険料の総額より増減することがあります。

学資保険は、貯蓄性の高い保険です。
さらに、終身保険や養老保険も貯蓄性の高い保険として挙げられます。
関連コラム
・ライフステージに合わせた終身保険の活用法!どんな人におすすめ?
・養老保険の契約時に確認しておくべき注意事項
学資保険のデメリットとは?
学資保険のメリットは、これまでお伝えした通り、子どもの将来の教育資金を確保できることや、生命保険料控除による節税効果があります。
しかし、一方で学資保険にはデメリットも存在します。
①運用利回りが低い
学資保険はあくまで貯蓄が目的であるため、他の投資商品に比べて運用利回りが低い傾向があります。
➁資金を自由に引き出すことができない
学資保険は長期間の契約が必要なため、資金を自由に引き出すことができません。
③途中解約の際のペナルティ
途中で契約を解約すると、支払った保険料に対して満期金が大幅に減少することがあります。

学資保険は、長期間の契約を前提にしているため、早期解約は不利になる場合があります。
保険について相談できるサイト
・生命保険に特化したFP無料相談
学資保険の種類
学資保険は、大きく分けて『貯蓄型』と『保障型』の2種類があります。
次に、この章では、それぞれの種類の特徴や、他の教育資金準備方法との違いについて詳しく見ていきましょう。
学資保険の2つのタイプ
先ほどお伝えした通り、学資保険は、大きく『貯蓄型』と『保障型』の2種類に分けられます。
これらのタイプにはそれぞれ異なる特徴があり、目的やニーズに応じて選ぶことが大切です。
1. 貯蓄型学資保険
貯蓄型学資保険は、将来の教育資金を計画的に積み立てることを目的とした商品です。
契約期間中に支払った保険料の一部が貯蓄として運用され、満期時にはまとまった金額を受け取ることができます。
教育資金が必要なタイミングに合わせて給付金を受け取ることができるため、計画的な資金準備が可能です。
2. 保障型学資保険
保障型学資保険は、契約者(親や保護者)が死亡または高度障害状態になった場合に、残された子どもに対して教育資金が支払われる商品です。
このタイプの保険は、万が一のリスクに備えつつ、教育資金の確保を目的としています。
保険について相談できるサイト
・生命保険に特化したFP無料相談
学資保険と他の教育資金準備方法の違い
学資保険と他の教育資金準備方法の違いを、下記図1にまとめてみます。
| 特徴 | 学資保険 | 預貯金 | 投資信託 / 株式投資 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 教育資金の確保と保障 | 自由な資金準備 | 高いリターンを狙う |
| 流動性 | 長期契約で資金を引き出せない | いつでも引き出せる | 売却可能だが市場リスクあり |
| リスク | 低リスク(保障あり) | 低リスク(元本保証) | 高リスク(元本保証なし) |
| 運用利回り | 低め(貯蓄目的) | 低い(利息が少ない) | 高いリターンの可能性(リスク伴う) |
| 税制面の優遇 | 生命保険料控除が適用 | 税制優遇なし | 税制優遇なし |
| 解約時のペナルティ | 早期解約時に満期金が減少することがある | なし | 売却時に損失の可能性 |

資産形成に関する情報は、以下の記事でまとめていますよ!
資産形成に関するオススメのコラム
・貯金ゼロからの資産増加法|初心者でもできる資産作りのポイント
学資保険は将来のライフプランニングをサポートする手段
将来の子どもの教育資金を確保できるということは、言い換えれば将来のライフプランニングをサポートすることになります。
最後に、学資保険がなぜライフプランニングの構築に役立つのかについて見ていきましょう。
将来の教育費用を見積れる
将来の教育費用を見積もることには、ライフプランニングにおいて、以下3つの重要な役割があります。
①計画的な資金準備
教育費用を見積もることで、必要な金額を把握し、計画的に教育資金を準備することができます。
②家計管理の向上
教育資金を見込むことで、家計全体の予算を見直すきっかけになります。
③ライフプランの策定
教育費用を明確にすることで、将来のライフプランを具体化しやすくなります。

つまり、学資保険もライフプランニングを向上させるための一つの手段ということです。
学資保険はライフプランに合わせた選択をする
学資保険は将来の教育資金を準備するための手段の一つであり、ライフプランに合わせた適切な選択をすることが大切です。
そのため、以下3つのステップを押さえておきましょう。
①将来のライフイベントを考慮する
教育資金だけでなく、住宅ローンや老後資金も視野に入れた全体的なライフプランを考えることが大切です。
②目標金額を設定する
学資保険で準備したい金額を設定し、そのために毎月どれだけ積み立てるかを計画します。
③保障内容の選択
学資保険には、万が一の保障がついている場合があるので、必要かどうかを考えて選択します。

ライフイベント表やキャッシュフロー表の作成は、ライフプランを明確にするための有効な手段です。
合わせて読みたいコラム
・ライフプラン表が必要な場面とは?計画的な人生設計をサポートする方法
・キャッシュフロー表の活用術:資産形成への道
まとめ
今回の記事のまとめです。
学資保険は、子どもの将来の教育資金を準備するための保険で、貯蓄と保障を兼ね備えています。
教育費の積み立てだけでなく、万が一の保障や税制面でのメリットもあるため、ライフプランに役立つ選択肢となります。
学資保険は主に、貯蓄型と保障型の2種類があり、それぞれのニーズに応じた選択が大切です。