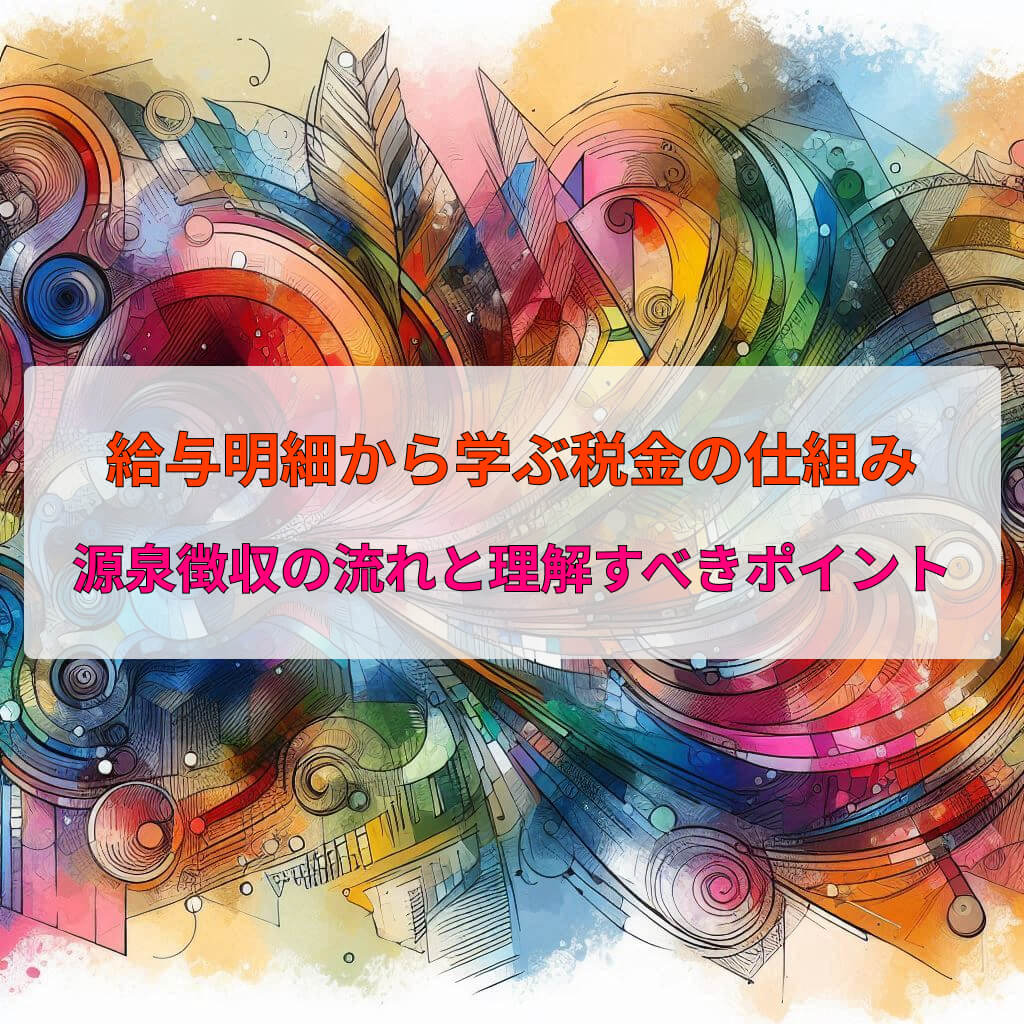『生命保険料控除って、実際どのくらいお得になるの?』
生命保険料控除は、所得控除のひとつです。
会社員は年末調整、個人事業主やフリーランスは確定申告で、それぞれ所得から控除を受けることができます。
しかし、その仕組みや控除の対象となる保険の種類を、意外と詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、生命保険料控除の概要や対象となる保険の種類について、分かりやすく解説していきます。
この記事で分かること
- 生命保険料控除の概要
- 生命保険料控除の種類
- 生命保険料控除の活用術

この控除を適切に活用することで、家計にどれほどの節税効果があるかを学んでいきましょう。
生命保険料控除とは?
そもそも、生命保険料控除とは、生命保険に加入している人が支払った保険料の一部を所得から控除できる制度です。
これにより、所得税や住民税の負担が軽減されます。
まず、生命保険料控除の基本的な仕組みを見ていきましょう。
生命保険料控除の基本的な仕組み
生命保険料控除について、押さえておきたい4つのポイントは以下の通りです。

控除対象となる保険料の種類や、控除上限額について、ポイントを押さえておきましょう。
①控除対象
・生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
➁控除額
・一般生命保険:年間最高控除額4万円
・介護医療保険:年間最高控除額4万円
・個人年金保険:年間最高控除額4万円
③所得控除の仕組み
・支払った保険料に応じた控除額が所得から差し引かれる。
・所得税や住民税は、収入から各種控除を引いた課税所得を基に計算される。
④申告方法
控除を受けるためには、確定申告または年末調整で保険料控除の申告が必要。

所得控除についての詳細は、以下のコラムをご参照ください。
参照コラム
・所得控除の仕組みと活用法
生命保険料控除のメリット
生命保険料控除のメリットとして、以下の2つが挙げられます。
①税負担の軽減
保険料控除を受けることで、実質的に税金を節約できるため、家計への負担を軽減できます。
➁資産形成の促進
可処分所得が増えることで、余剰資金を貯金や投資に回しやすくなり、資産形成が計画的に促進される可能性があります。

可処分所得とは、税金や社会保険料を差し引いた後に自由に使えるお金のことを指します。
合わせて読みたいコラム
・可処分所得とは?年末調整の気になる悩み
控除対象となる保険の種類
先ほどの章で、生命保険料控除には一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3つが含まれるとお伝えしました。
次に、この章では、控除対象となる保険の種類について詳しく見ていきましょう。

以下図1の表は、生命保険料控除の対象となる保険の種類を示しています。
| 生命保険料控除名 | 対象となる保険 |
|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 定期保険、終身保険、学資保険、収入保障保険 |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険 |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険、確定年金保険、変額年金保険 |
一般生命保険料控除
一般生命保険料控除は、生存または死亡に基づいて一定額の保険金や給付金が支払われる保険が対象となります。
具体的には、以下のような保険が該当します。
定期保険
一定期間内に死亡した場合に保険金が支払われる保険。
終身保険
保険契約者が死亡するまで保障が続く保険で、生存中でも解約返戻金がある場合がある。
学資保険
子どもの教育資金を目的とした保険で、契約期間満了時に満期保険金が支払われるものや、契約者の死亡時に保険金が支払われるものがある。
収入保障保険
契約者が死亡または所定の条件に該当した場合に、一定の期間にわたって毎月保険金が支払われる保険。
一般生命保険に関するコラム
・学資保険のメリットとデメリット、教育資金準備方法を総まとめ
・収入保障保険を活用したリスクマネジメント
介護医療保険料控除
介護医療保険料控除は、介護や医療に関する保険料を支払った場合に、所得から控除を受けることができる制度です。
この控除は、被保険者が医療や介護に対する備えをしていることを考慮したもので、具体的には以下のような保険が対象となります。
医療保険
入院や通院などの医療費を保障するための保険。
がん保険
がんの診断や治療にかかる費用を保障するための保険。
介護保険
介護が必要になった場合に備えるための保険。
就業不能保険
疾病や事故によって働けなくなった場合に、所得を補償するための保険。
介護医療保険料に関するコラム
・限定告知型医療保険のメリットと注意点|通常の医療保険とどう違う?
・就業不能保険で備えるべきリスクとは?
個人年金保険料控除
個人年金保険料控除の対象となるのは、税制適格特約が付帯された個人年金保険契約です。
具体的には以下のような保険が含まれます。
個人年金保険
定期的に年金を受け取ることができる保険。老後の生活資金を計画的に準備するためのもので、一定期間または終身にわたり年金が支払われます。

つまり対象となるのは、税制適格特約が付いた個人年金保険のみということです。
個人年金保険に関するコラム
・個人年金保険の選び方:運用方法の違いとその影響を理解する
生命保険料控除の算出方法
最後に、生命保険料控除の算出方法について見ていきましょう。
保険料の算出方法は、新制度(2012年1月1日以降の契約)と旧制度(2011年12月31日以前の契約)で異なるため、それぞれについて見ていきましょう。
所得税と住民税に適用される控除額(2012年1月1日以降の契約)
以下に、新制度以降(2012年1月1日以降の契約)の所得税と住民税における生命保険料控除額を、表形式で示します。

ざっくりとした目安として、年間の保険料を基に控除額を確認してみてください。
所得税の控除額(2012年1月1日以降の契約)
| 年間の保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 2万円超4万円以下 | 払込保険料等 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 払込保険料等 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律 4万円 |
住民税の控除額(2012年1月1日以降の契約)
| 年間の保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 1万2,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 1万2,000円超3万2,000円以下 | 払込保険料等 × 1/2 + 6,000円 |
| 3万2,000円超5万6,000円以下 | 払込保険料等 × 1/4 + 1万4,000円 |
| 5万6,000円超 | 一律 2万8,000円 |
所得税と住民税に適用される控除額(2011年12月31日以前の契約)
次に、旧制度(2011年12月31日以前の契約)の所得税および住民税における生命保険料控除額を、それぞれ表形式で提示します。
所得税の控除額(2011年12月31日以前の契約)
| 年間の保険料等 | 控除額 |
| 2万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 2万5,000円超5万円以下 | 払込保険料等×1/2+1万2,500円 |
| 5万円超10万円以下 | 払込保険料等×1/4+2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
住民税の控除額(2011年12月31日以前の契約)
| 年間の保険料等 | 控除額 |
| 1万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 1万5,000円超4万円以下 | 払込保険料等×1/2+7,500円 |
| 4万円超7万円以下 | 払込保険料等×1/4+1万7,500円 |
| 7万円超 | 一律3万5,000円 |

国税庁のサイトで控除額を確認できますが、詳細が必要な場合は専門家に相談するのも一つの方法ですよ!
まとめ
今回の記事のまとめです。
生命保険料控除は、生命保険に加入している方が支払った保険料の一部を所得から控除できる制度です。
この制度を利用することで、所得税や住民税の負担が軽減され、控除額は年間に支払った保険料に基づいて計算されます。
ただし、保険料の控除額は新制度と旧制度で異なるため、注意が必要です。