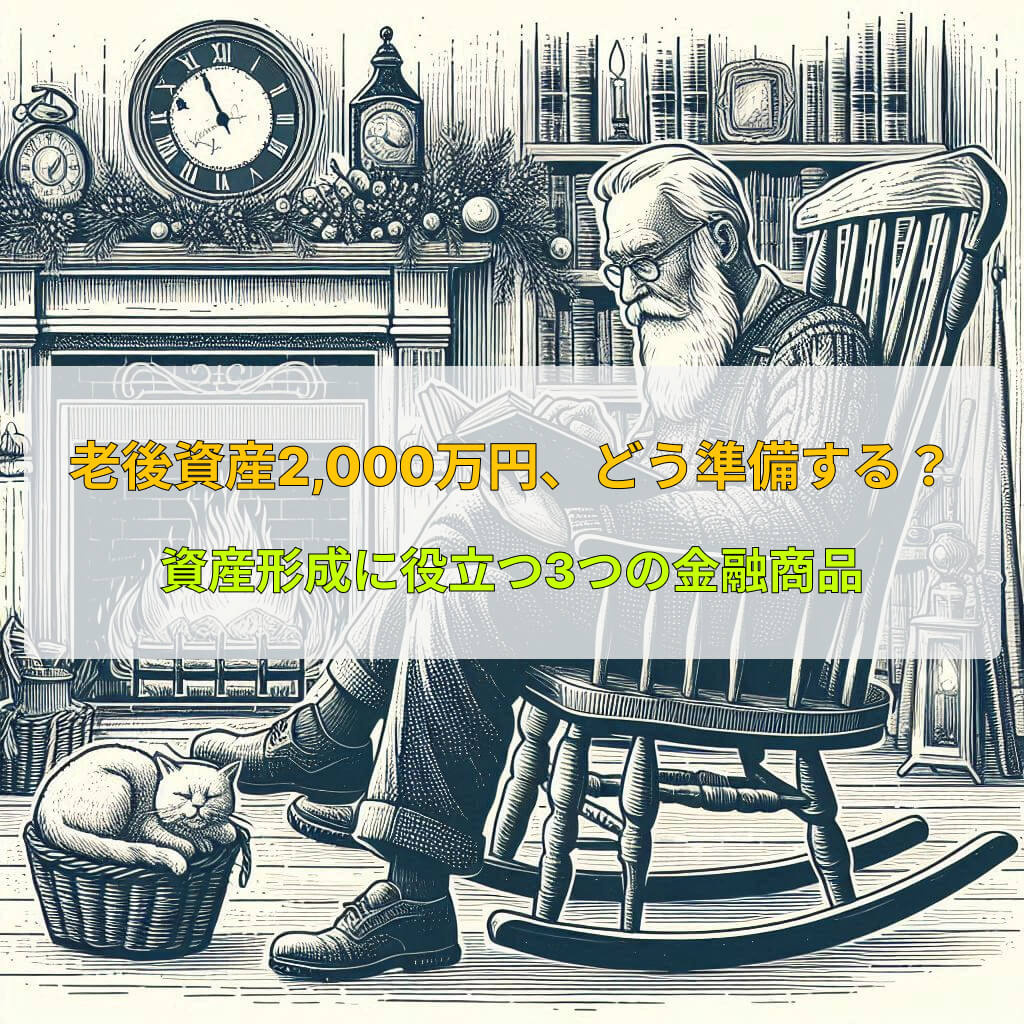『年金受給額だけでは生活が苦しい——』
これは筆者の祖母がよく口にする言葉です。
高齢化が進む現代社会において、高齢者の可処分所得はますます重要なテーマとなっています。
本記事では、公的年金が高齢者の可処分所得にどのように関与しているかを詳しく考察し、高齢者が可処分所得を増やすための具体的な方法についても解説していきます。
この記事で分かること
- 高齢者にとっての可処分所得の役割
- 公的年金が可処分所得に与える影響
- 高齢者が可処分所得を増やすための対策

可処分所得とは、税金や社会保険料を引いた後に手元に残る自由に使えるお金を指します。
高齢者にとっての可処分所得の役割
同じ可処分所得であっても、高齢者と若年層では生活スタイルや支出内容が異なります。
まずは、高齢者にとって可処分所得がどのような役割を果たすのかを見ていきましょう。
可処分所得の増加が生活の質を向上させる理由
高齢者が可処分所得を増やすことで得られるメリットは、主に以下の3つの要因に集約されます。
①経済的安定の確保
可処分所得が増えることで、必要な生活費や医療費、介護サービスの支出を捻出できるようになり、将来の医療費や介護費用、予期せぬ支出にも備えることができます。
➁健康管理の向上
経済的余裕が生まれることで、質の高い医療サービスや健康サポートを受けやすくなり、健康状態の維持・改善が期待できます。
③趣味・娯楽への投資
可処分所得が増えることで、趣味や地域活動に参加しやすくなり、社会的なつながりが強化され、セカンドライフが充実しやすくなります。

可処分所得については、以下のコラムで詳しく解説しています。
合わせて読みたいコラム
・可処分所得を有効化するための3つのポイント
公的年金が可処分所得に与える影響
次に、公的年金の基礎知識について見ていきます。
一般的に、高齢者の生活における主な収入源は公的年金であるため、その概要をこの章で把握しておきましょう。
公的年金の仕組み
公的年金は、国が運営する年金制度で、主に国民年金(基礎年金)と厚生年金の2つから成り立っています。
国民年金は、すべての国民が加入する基本的な制度で、20歳以上60歳未満の人に加入義務があります。
一方、厚生年金は会社員や公務員を対象としており、国民年金に追加される形で支給されます。

さらに、年金保険の三階建て部分には、私的年金が含まれています。
合わせて読みたいコラム
・第三の年金とは?企業年金の仕組みをわかりやすく解説
年金受給額と可処分所得の関係
年金受給額と可処分所得は、特に高齢者にとって密接な関係があります。
年金が主要な収入源となる場合が多い中で、年金受給額は高齢者の生活基盤となるため、年金から差し引かれる税金や社会保険料の負担が可処分所得を左右します。
具体的には、以下2つのような影響があります。
①税金・社会保険料の影響
年金受給額が一定額以上になると、所得税や住民税、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料が天引きされ、実際に手元に残る可処分所得はこれらの負担分を差し引いた額となります。
②非課税基準の適用
年金受給者には非課税基準が適用され、基準以下の年金受給額であれば、住民税や介護保険料の負担が減り、可処分所得が増えることがあります。
年金について相談できるサイト
・老後資金に特化したFP無料相談
高齢者が可処分所得を増やすための対策
高齢者が若年層と大きく異なる点は、収入源が減少することです。
特に、年金が主要な収入源となる中で、若年層に比べて収入の柔軟性が限られてしまいます。
では、最後に、高齢者が可処分所得を増やすための具体的な方法を見ていきましょう。
生活費の見直し
高齢者が可処分所得を増やすためには、まず生活費の見直しが有効な対策の一つです。
日々の支出を効率化することで、手元に残るお金を増やし、結果的に可処分所得を高めることができます。
具体的には、以下の3つのポイントが効果的です。
①固定費の削減
固定費は毎月必ずかかる支出のため、見直しによって長期的な節約効果が期待できます。たとえば、携帯電話のプランの見直しや電力会社の変更を検討することで、毎月の支出を減らすことが可能です。
➁食費や日用品の工夫
高齢者向けの割引を活用したり、まとめ買いや特売日を利用するなど、食費の節約方法を工夫することで、日々の支出を抑えることができます。
③住居費の見直し
住まいが広すぎる場合や住宅ローンの負担が大きい場合、賃料の見直しや住宅ローンの借り換え、リバースモーゲージの活用により住居費を軽減することができます。

地方移住や海外移住など、生活基盤を変更することも一つの選択肢です。
参照コラム
・海外移住|老後、シニア世代にやさしい国5選をご紹介
保険の見直し
高齢者が可処分所得を増やすには、保険の見直しも有効です。
保険は固定費として長期間支払うため、内容を見直すことで支出を抑え、手元に残るお金を増やせます。
保険の見直しの3つのポイントは、以下の通りです。
①保険の整理
不要な保険料を削減するために、特に独立した子どもがいる場合や過剰な保障がある場合は、保障額を減らしたり解約することが有効です。
➁医療保険の適切な見直し
医療保険は重要ですが、すでに公的医療保険で保障される部分もあるため、重複する保障や利用頻度が低い特約を外すことで、保険料を抑えられます。
③介護保険の検討
将来の介護に備えるため、民間の介護保険も検討できますが、公的介護保険で十分かどうかも考慮し、費用対効果を見極めることが大切です。

保険は一度加入すると放置しがちですが、定期的に見直すことで内容や月々の支払い負担を最適化できます。
参照コラム
・保険の相談窓口とは?おすすめの保険相談窓口8社を比較!
公的支援や補助金の活用
高齢者が可処分所得を増やす方法に、公的支援や補助金の活用が挙げられます。
これらの公的支援を利用することで、生活費を軽減し、手元に残る資金を増やすことができます。
具体的な活用方法は、主に以下の3つです。
①年金以外の公的支援の確認
高齢者には、生活支援や医療、介護に関するさまざまな公的支援が用意されています。たとえば、低所得者向けの生活保護や医療費の一部助成制度があります。
➁補助金の活用
各自治体では、高齢者向けの補助金や助成金が用意されています。具体的には、介護サービスを利用する際の補助金や、住宅のバリアフリー改修に対する助成金などがあります。
③税制上の優遇措置
高齢者には、税金の減免や優遇措置が適用されることがあります。たとえば、住民税の非課税措置や医療費控除などです。

公的支援や補助金はすべての人に適用されるわけではありませんが、まずは自身が対象者に該当するかどうかを確認し、相談してみることが大切です。
合わせて読みたいコラム
・FPに相談するメリットとは?お金と保険の専門家だからできること
まとめ
今回の記事のまとめです。
高齢者にとって、年金受給額は生活基盤を支える重要な要素ですが、年金から差し引かれる税金や社会保険料が可処分所得に大きな影響を与えるため、これらの負担をしっかりと考慮することが大切です。
可処分所得を増やすことには、以下の3つのメリットがあります。
①経済的安定の確保
②健康管理の向上
③趣味や娯楽への投資
可処分所得を増やすためには、生活費や保険の見直し、公的支援や補助金の活用が有効な手段となります。