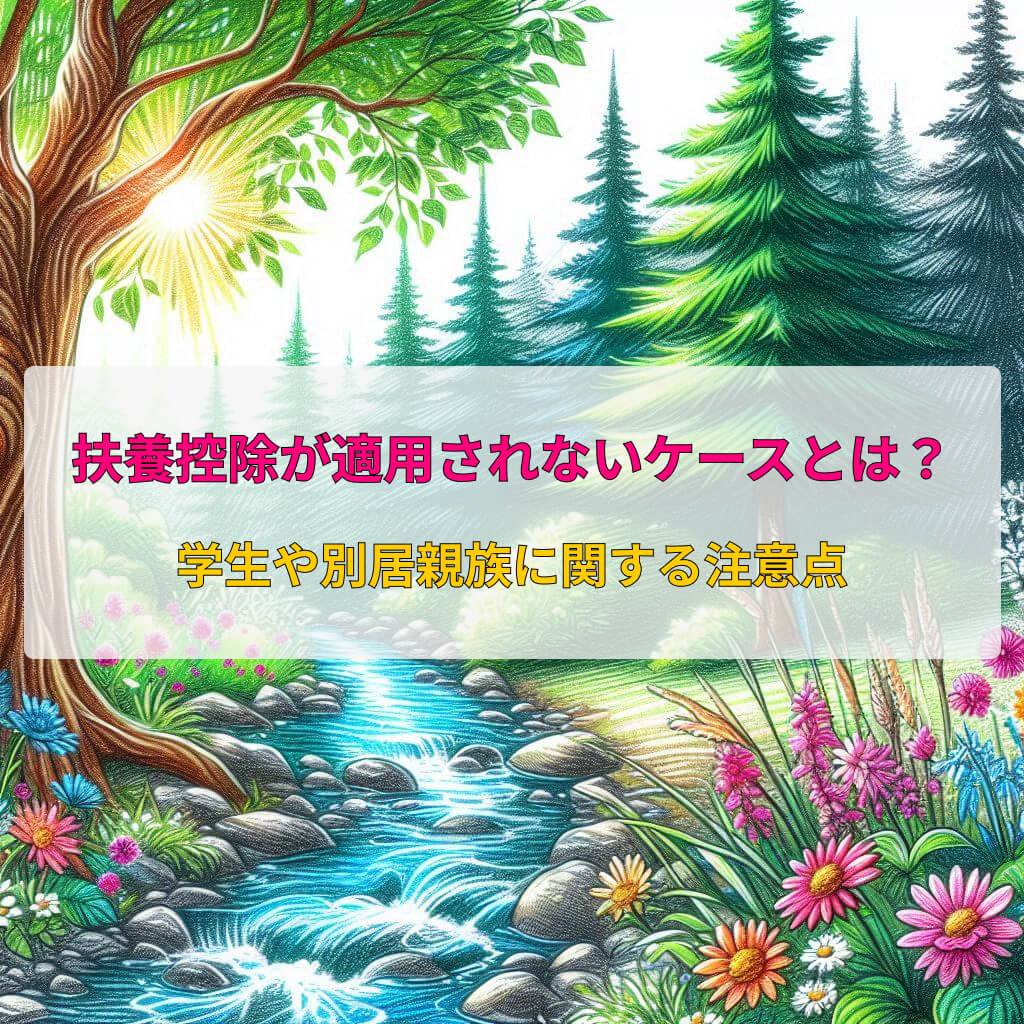『シニア世代を扶養に入れるメリットとは?』
シニア世代(65歳以上)を扶養に入れることで、税制面でのメリットが大きく、適切に活用すれば所得税や住民税の負担を軽減できます。
ただし、扶養に入れるには、適用される年齢や扶養者の所得など、いくつかの条件を理解しておく必要があります。
この記事では、シニア世代を扶養に入れることで得られる税制面のメリットに加え、扶養控除に関するよくある質問(Q&A)についても解説していきます。
この記事で分かること
- シニア世代を扶養に入れるメリット
- シニア世代を扶養に入れる際の注意点
- 扶養控除に関するQ&A

シニア世代(65歳以上)が扶養控除を受けるための条件を確認していきましょう。
※この記事でのシニア世代とは、65歳以上の定年退職者を前提としています。
扶養控除を活用して税金を軽減する方法
扶養控除には対象範囲や条件がありますが、シニア世代を扶養に入れることで、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
まずは、シニア世代を扶養に入れることのメリットを見ていきましょう。

『老人扶養親族』とは、70歳以上で老人扶養控除を受けている親族を指します。
シニア世代を扶養に入れるメリットとは?
シニア世代を扶養に入れるメリットには、主に税制面での優遇があります。

その具体的なメリットには、以下の3つが挙げられます。
1. 扶養控除による税金の軽減
シニア世代(65歳以上)を扶養に入れると、所得税や住民税が軽減され、70歳以上では「老人扶養控除」が適用されて控除額が増加します。
2. 社会保険料の負担軽減
シニア世代を扶養に入れることで、健康保険の被扶養者となり、保険料の支払いが不要になったり、医療費の自己負担割合が減少することがあります。
3. 生活支援や支援制度の利用
シニア世代を扶養に入れることで、介護保険や高齢者向け支援金制度など、福祉制度や生活支援制度の利用資格を得やすくなります。
参照サイト
・国税庁『No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除』
シニア世代の扶養で得られる所得控除とは
シニア世代(65歳以上)を扶養に入れることで受けられる所得控除には、主に以下の5つが挙げられます。
1. 扶養控除(老人扶養控除)
扶養している家族がいる場合、特にシニア世代(70歳以上)を扶養に入れると「老人扶養親族」として扱われ、通常の扶養控除よりも控除額が増えます。
2. 医療費控除(特別支援)
シニア世代を扶養に入れている場合、年間医療費が一定額を超えると、その超過分を医療費控除として申請し、所得税や住民税を軽減できます。
3. 社会保険料控除
扶養しているシニア世代が支払った社会保険料は社会保険料控除として申告でき、税負担を軽減できます。
4. 介護保険料控除
シニア世代を扶養している場合、介護保険料の支払い金額は社会保険料控除として申請でき、税負担を軽減できます。
5. 配偶者控除
65歳以上のシニア世代の配偶者が年間所得48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であれば「配偶者控除」が適用されます。

ただし、配偶者控除は扶養控除と併用できない場合があるため、注意が必要です。
合わせて読みたいコラム
・配偶者控除×扶養控除でできる節税術
シニア世代を扶養に入れる際の注意点と要件
次に、シニア世代を扶養に入れる際の注意点を見ていきます。
前述のように、併用できない控除もあるため、その条件についてさらに詳しく確認していきましょう。
シニア世代を扶養に入れる際の注意点と要件
シニア世代を扶養に入れる際の注意点として、以下の4点を確認しておくことが大切です。
1. 所得制限と扶養控除の適用条件
シニア世代(65歳以上)の扶養控除を受けるためには、扶養される方の年間所得が一定額以下であることが必要です。
扶養されるシニアの年間所得上限額
Ⓐ所得制限
・扶養されるシニア世代の年間所得が48万円以下であることが条件(令和元年分以前は38万円以下)。
Ⓑ給与所得がある場合
・シニア世代が給与所得者の場合、給与収入が103万円以下でなければ扶養控除の対象外。
2. 併用できない控除の把握
シニア世代を扶養に入れる場合、配偶者控除と扶養控除は同一の配偶者に対して併用できません。
配偶者控除を受けるためには、配偶者の年収が一定額(通常は年収103万円以下)である必要があります。
参照コラム
・配偶者控除の所得制限をクリアするための要点とは?
3. 扶養親族としての要件
シニア世代が扶養親族として認められるためには、納税者と「生計を一にしている」ことが必要です。
つまり、シニア世代が独立して生活しておらず、納税者と共同で生活費を負担している状態でなければなりません。
もし別居している場合でも、生活費の支援をしていることが証明できれば扶養親族として認められます。

扶養に入れる親族が同居か別居かによって、控除金額が異なります。
69歳以下:控除額38万円
70歳以上で扶養者と別居:控除額48万円
70歳以上で扶養者と同居:控除額58万円
4. 青色申告者の事業専従者について
シニア世代が青色申告者の事業専従者として働いている場合、その年に一度も給与を受け取っていないことが要件です。
もし給与を受け取っている場合、扶養控除の対象外となる場合があります。
また、白色申告者の事業専従者であっても同様の扱いになります。
よくある質問|扶養控除に関するQ&A
最後に、扶養控除に関するよくある悩みについて見ていきましょう。
再三お話ししてきたように、扶養控除には適用条件が定められています。
ここでは、実際によくある質問を通じて、扶養控除の疑問を解消しておきましょう。
扶養控除と医療費控除の併用で気を付けることとは?
扶養控除と医療費控除を併用する際には、以下の3点に注意が必要です。
1. 申告対象となる扶養親族の把握
医療費控除の対象となるのは、納税者本人やその扶養親族が支払った医療費であり、対象外となる費用もあるため、控除を受ける前に何が対象となるかをしっかりと確認することが重要です。
2.医療費控除に必要な証明書の準備
扶養控除を受けているシニア世代や扶養親族の医療費は医療費控除に含められますが、支払いを証明する領収書などが必要です。
3. 確定申告を通じての申告
扶養控除と医療費控除を両方適用する場合、確定申告を通じて申請する必要があり、年末調整では申告できません。
合わせて読みたいコラム
・医療費控除とセルフメディケーション税制を使ったシミュレーション
扶養控除の対象となる親族範囲はどこまで?
扶養控除の対象となる親族は、以下の条件を満たす者です。
・納税者の配偶者(内縁関係の人は除く)
・子ども(実子、養子、または養子縁組をしている孫など)
・父母(実親、養親、義父母)
・祖父母(親の両親、義両親)
・兄弟姉妹(納税者と血縁関係のある兄弟姉妹やその子ども)
・その他の親族(直系血族、兄弟姉妹の子など)

扶養控除の適用範囲については、以下のコラムで詳しく解説しています。
合わせて読みたいコラム
・扶養控除が適用されないケースとは?学生や別居親族に関する注意点
まとめ
今回の記事のまとめです。
シニア世代を扶養に入れることで、税制面や社会保険面でのメリットがあります。
特に70歳以上のシニアを扶養に入れる場合、「老人扶養控除」が適用され、通常の扶養控除よりも控除額が増えるため、税負担が軽減されます。
ただし、扶養されるシニアの年間所得には制限があり、また、配偶者控除と扶養控除は併用できません。
扶養控除を適用する際は、これらの条件を確認し、適切に申告することが重要です。
※この記事は令和6年11月時点で執筆したものです。控除額は今後変更される可能性がございますので、最新の情報については国税庁の公式サイトをご確認くださいますようお願い申し上げます。