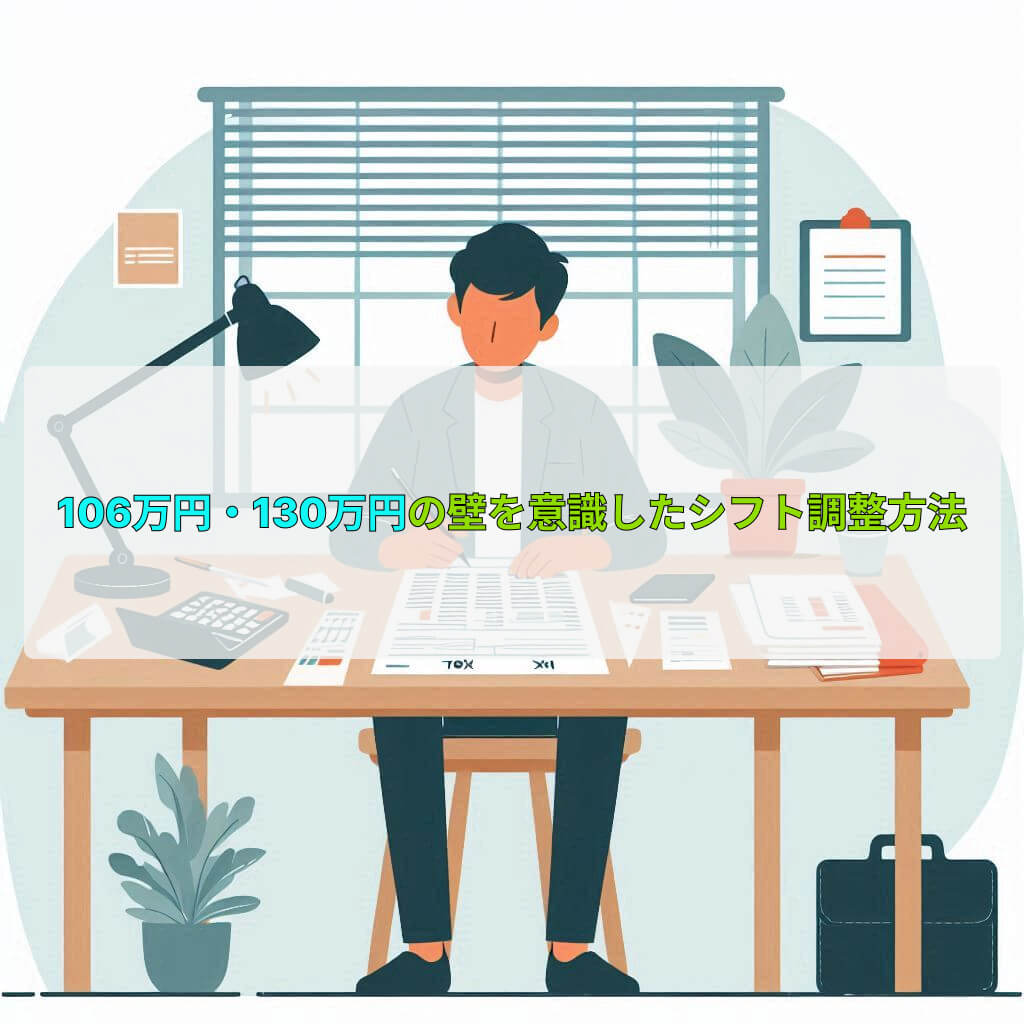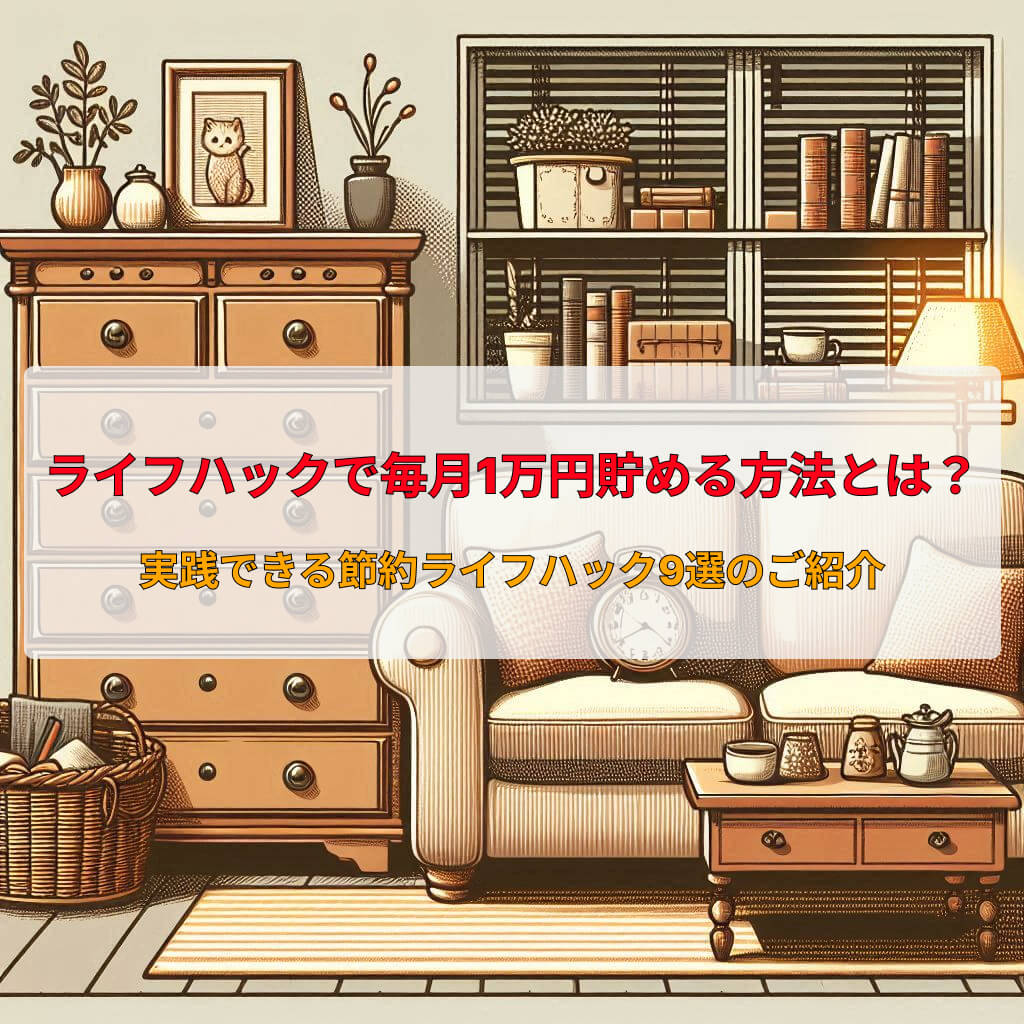近年、「働き控え」という言葉が注目を集めています。
これは、パートやアルバイト、専業主婦の方が一定の収入を超えないように働き方を調整することを指します。
しかし、多くの方が103万円の壁や130万円の壁を意識するあまり、知らないうちに損をしてしまうケースが増えている傾向があります。
本記事では、働き控えによる収入の損失を防ぐために、知っておきたいリスク管理のポイントを解説します。
この記事で分かること
- 働き控えが起こる背景とそのリスク
- 働き控えによって生じる収入面での損失
- 働き控えを解消して家計を改善する3つの方法

働き控えによって、どのようなリスクがあるのかを一緒に学んでいきましょう。
働き控えとは?その背景と原因を解説
日常生活では『働き控え』という言葉を耳にすることは少ないかもしれませんが、実際には多くの人が選択している働き方の一つです。
まず最初に、働き控えの概要について見ていきましょう。
働き控えの定義とその現状とは?
働き控えとは、世帯全体の税金や社会保険料の負担を抑えるために、意図的に労働時間や収入を制限する働き方を指します。
特に日本では、配偶者控除や扶養控除、社会保険の加入基準が所得に連動しており、一定の収入ラインを超えると税負担が増加します。
そのため、多くの人がそのラインを超えないように収入を調整する傾向があります。

働き控えが発生する主な要因には、以下の3つがあります。
①103万円の壁(所得税)
パートやアルバイトの年間収入が103万円以下であれば、所得税が非課税となります。
➁130万円の壁(社会保険)
年間収入が130万円を超えると被扶養者から外れ、社会保険料を自己負担することになります。
③106万円の壁(社会保険適用拡大)
週20時間以上勤務し、年収が106万円を超える場合、従業員数101人以上の企業では厚生年金と健康保険への加入が義務となります(2024年10月以降は50人以上の企業が対象に拡大)。

103万円の壁については、以下のコラムで詳しく解説しています。
参照コラム
・パート収入での定額減税、103万円超の注意点
106万円の壁と130万円の壁の違い
「106万円の壁」と「130万円の壁」は、それぞれ異なる社会保険の適用基準に関連しており、これらの基準を超えると収入が減少する可能性があります。

以下に、それぞれの適用条件を確認してみましょう。
106万円の壁
加入制度
厚生年金保険・健康保険
対象
従業員101人以上の企業に勤務し、週20時間以上働いている場合(2024年10月以降、対象企業が50人以上に拡大)
影響
配偶者や扶養家族の年収が106万円を超えると、原則として国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。
130万円の壁
加入制度
国民年金・国民健康保険
対象
従業員100人以下の企業などに勤務している場合(106万円の壁に該当しない場合)
影響
配偶者や扶養家族の年収が130万円を超えると、原則として国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。

130万円の壁対策として、一時的に収入が130万円を超えても、事業主がその旨を証明すれば、引き続き扶養に入ることが可能です。
130万円の壁対策に関する参照サイト
・年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省
103万円・130万円の壁がもたらす影響とは
「103万円の壁」は主に所得税、「130万円の壁」は社会保険料に関する基準です。
これらの壁を意識しながら働くことで、家計の負担が軽減され、より効率的な家計管理が可能になります。

103万円の壁と130万円の壁の違いを押さえておきましょう。
103万円の壁
①所得税が非課税
年間収入が103万円以下であれば、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)により、所得税がかかりません。
➁配偶者控除の適用
収入が103万円以内の場合、配偶者が「配偶者控除」を受けられ、世帯全体の所得税が軽減されます。
130万円の壁
①社会保険料の負担発生
年間収入が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、自身で健康保険や厚生年金に加入する必要があります(収入の約14%が保険料として控除)。
➁家計への影響
社会保険料の支払いにより、世帯全体の可処分所得が減少し、家計管理に影響を与えます。

可処分所得について、以下のコラムをご参照ください。
合わせて読みたいコラム
・可処分所得を有効化するための3つのポイント
働き控えによる損失とは?知っておくべきリスク管理
お伝えした通り、年収が一定のラインを超えると、所得税や社会保険料の負担が増え、手取り収入が減少する可能性があります。
この章では、収入減少が家計に与える影響について考えていきます。
収入減少による家計への影響
所得税や社会保険料が増加すると、手取り収入が減少し、生活費や貯金計画、将来の資産形成に影響を与える可能性があります。

具体的には、税負担の増加により、以下の2つの影響が考えられます。
1. 自由に使えるお金の減少
年収が一定額を超えると、課税対象となる所得が増え、それに伴い所得税が増加します。
例えば、「103万円の壁」を超えると、配偶者控除が適用されなくなり、その分、税負担が増えます。
このような増税は、家計の自由に使えるお金が減少することを意味します。
2. 貯蓄や投資に回す資金の減少
年収が「130万円の壁」などを超えると、社会保険に加入することが義務付けられ、健康保険や厚生年金保険の保険料を自己負担することになります。
社会保険料は収入の約14%程度になるため、手取りが大きく減少することになります。
これにより、生活費に充てる金額が減ることに加えて、貯蓄や投資に回す資金が減少する可能性があります。
参照コラム
・標準報酬月額ってどのように求めるの?
将来受け取る年金への影響
年収の壁範囲内で働くことで納税額を抑えるメリットがありますが、同時に将来の年金受給額が減少するリスクも伴います。
特に、働き控えが続く場合、老後の生活資金に大きな影響を及ぼす可能性があります。

年金受給額の減少に関するリスクとして、以下の2つが考えられます。
①労働の継続と貯蓄の切り崩し
年金受給額が少ない場合、老後に必要な医療費や介護費用を賄うための資金が不足する恐れがあります。
今後、老後の生活費や医療・介護費用は膨らんでいくと予想した場合、年金が減少すると以下の2つの影響が考えられます。
1. 貯蓄の切り崩し
生活費や医療・介護費用をまかなうために、貯蓄を取り崩さざるを得ない可能性があります。
2. 働き続ける必要が生じる
年金だけでは生活が成り立たず、老後も働き続けなければならない状況に陥る可能性があります。
②厚生年金への加入期間が短くなるリスク
働き控えによって社会保険(特に厚生年金)への加入期間が短くなると、将来受け取る年金額が減少します。
年金額は過去の収入に基づいて計算されるため、加入期間が短いと十分な年金を受け取れない可能性があります。
現在の納税額を減らすことができる一方で、将来の年金受給額が減少するリスクも存在するということですね。

そうです。そのため、第三の年金などの資産形成は重要な手段となります。
働き控えを解消し、家計を改善する3つの実践ステップ
最後に、働き控えの解消と家計改善につながる3つの方法をご紹介します。
先ほどの章では第三の年金での資産形成に触れましたが、今回はそれ以外の視点から考えてみましょう。
1. 家計見直しと収支バランスの再確認
家計を改善するためには、単に支出を削減するだけでなく、収支のバランスを見直し、効率的にお金を使う方法を取り入れることが重要です。

家計や収支バランスを見直すために、次の3つのポイントを確認してみましょう。
①収入源の多角化
収入源を一つに頼らず、副収入や投資などで複数の収入を確保することで、家計の安定性が高まり、予期せぬ支出にも対応しやすくなります。
②支出の優先順位を見直す
必要な支出(住宅ローン、教育費、医療費など)を優先し、不必要な支出を減らして予算を組み直すことが重要です。
③支出の未来予測と先取り管理
現在と将来の支出を予測し、積立や資産運用を計画することで、将来のリスクに備えた家計管理が可能になります。
2. 収入アップを目指す資格取得やスキル磨き
働き控えを解消し、家計を改善するためには、資格取得やスキル磨きも有効な手段です。
これらを活用することで、自身の市場価値を高め、収入アップのチャンスが広がります。
例えば、ITスキルや語学力、医療・福祉の資格など、自身の業界に合わせた資格を取得することは、転職や昇進を有利に進めるために効果的です。
さらに、専門的なスキルを磨くことで、フリーランスとしての独立や副業の選択肢も広がり、収入の増加が期待できます。

資格取得やスキルアップに関する詳細は、以下のコラムをご参照ください。
合わせて読みたいコラム
・副業に必要なスキルとは?副業初心者が身につけるべき3つのスキル
3. ファイナンシャルプランナーに相談して最適なプランを立てる
ファイナンシャルプランナー(FP)に相談し、最適なプランを立てることは、働き控えを解消し、家計を改善するために効果的な方法です。

FPに相談することのメリットには、以下3つがありますよ!
①家計全体の見直しができる
FPは家計の収支を総合的に分析し、無駄な支出を削減する方法を提案するとともに、将来に向けた効率的な支出計画を立ててくれます。
②節税に関するアドバイスが受けられる
FPは、ふるさと納税やiDeCoなどを活用した節税対策を提案し、税負担を軽減する方法をアドバイスしてくれます。
③資産形成に関する相談ができる
FPは、将来に向けた資産形成をサポートし、リスク許容度に応じた投資計画を立てて、安定した資産運用の方法を提案してくれます。
FPに無料相談できるサイト
・家計見直しに特化したFP無料相談
まとめ
今回の記事のまとめです。
働き控えとは、税金や社会保険料の負担を抑えるために、意図的に収入を一定の範囲に抑えることを指します。
主に「103万円」「130万円」「106万円」といった収入の壁が存在し、これらを超えると税金や社会保険料の負担が増える仕組みです。
働き控えには、短期的に負担を軽減できるメリットがある一方で、長期的には年金受給額の減少や、老後の生活資金が不足するリスクがある点に注意が必要です。
※この記事は令和6年11月時点で執筆したものです。最新の情報については国税庁の公式サイトをご確認くださいますようお願い申し上げます。