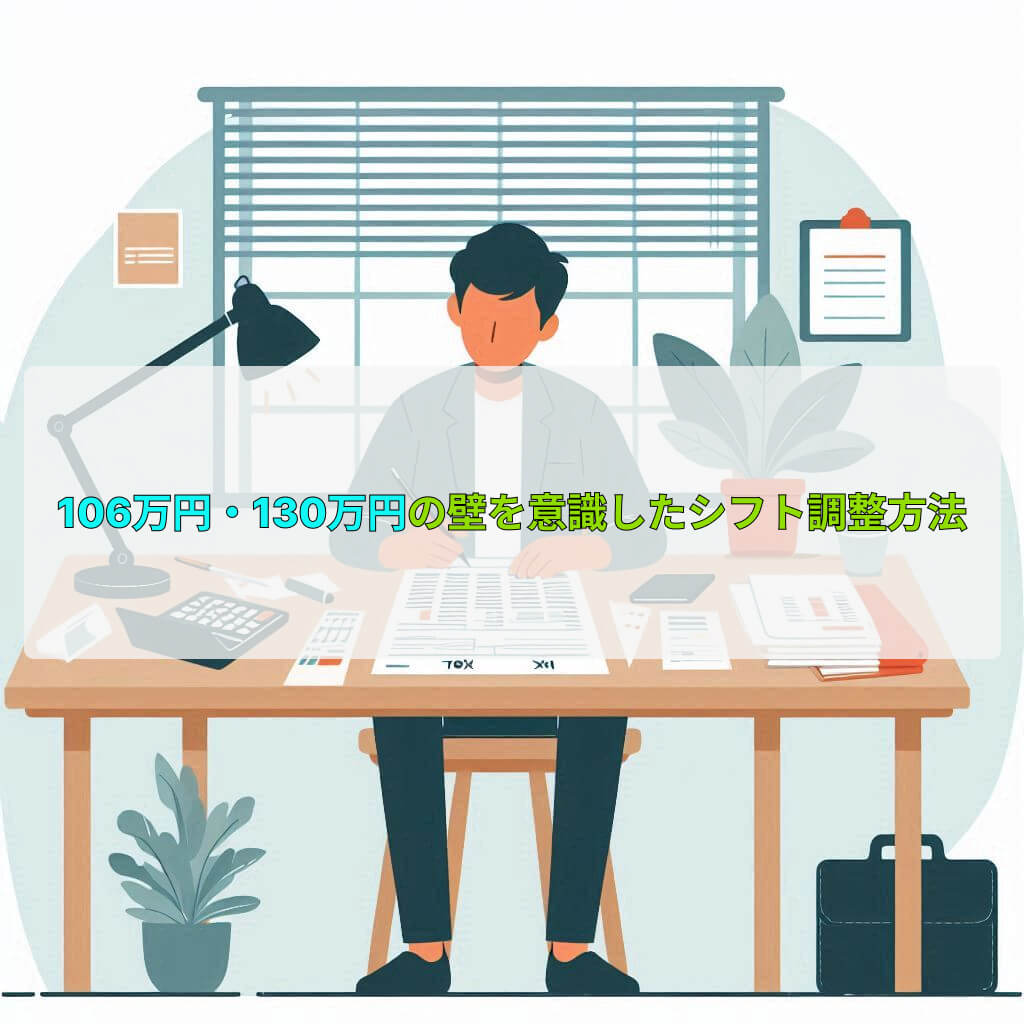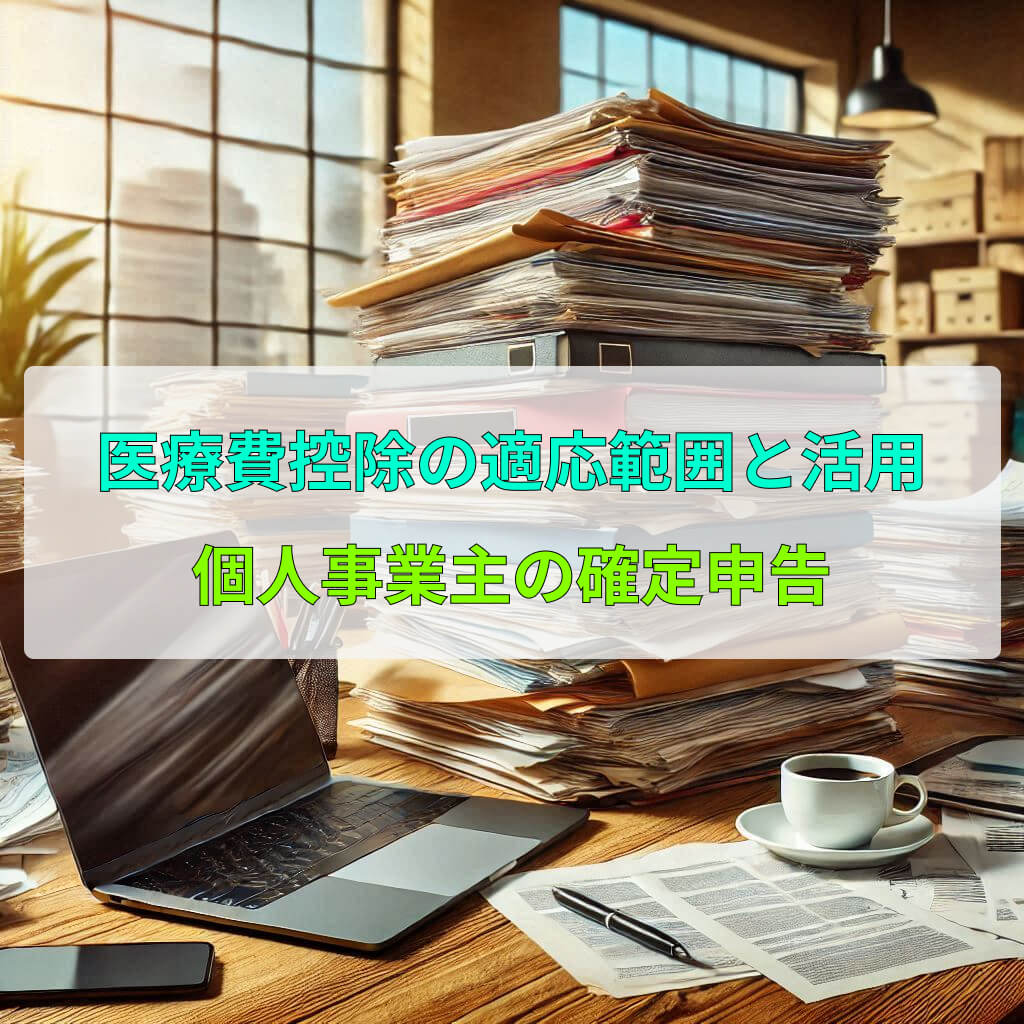寄付金控除は、税負担を軽減するための有効な手段の一つですが、実は他にもさまざまな税制優遇制度があります。
例えば、ふるさと納税や個人年金の寄付、生命保険料控除など、寄付金控除と組み合わせることで、さらに税金を抑えることが可能です。
この記事では、寄付金控除とその他の税制優遇制度の関連性を詳しく解説し、それらを活用することで自身の納税額がどのように変化するのかについてをお伝えしていきます。
この記事で分かること
- 寄付金控除と医療費控除との関係
- 寄付金控除と生命保険料控除の併用
- 寄付金控除と住宅ローン控除の併用

今回は、寄付金控除を他の3つの控除と併用する際のポイントについての解説です。
寄付金控除と医療費控除との関係
寄付金控除と医療費控除は、いずれも税制上の優遇措置ですが、それぞれ異なる要件に基づいて適用されます。
両者は独立した控除であるため、同一年度に両方を適用することが可能です。
まず最初に、寄付金控除と医療費控除を併用する際の注意点について解説します。
医療費控除と寄付金控除の違い:6つのポイント
寄付金控除と医療費控除は、どちらも税負担の軽減を目的とした制度ですが、それぞれ目的や対象が異なります。
以下に、その違いを6つのポイントでご紹介します。
1. 寄付金控除と医療費控除の関係
寄付金控除と医療費控除は、それぞれ異なる種類の支出に対して適用される控除ですが、同一の税年度において両方を申請することが可能です。
寄付金控除
寄付金額(自己負担額を除く)に対して所得税や住民税の控除が適用されます。例えば、ふるさと納税などに寄付をした場合、その寄付金額から自己負担の2,000円を差し引いた金額が控除の対象となります。
医療費控除
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分について控除が適用されます。医療費控除は、自己負担額の合計が一定の基準を超えた場合に、その超過分について税額控除を受けることができます。
2. 同時に申請できる
寄付金控除と医療費控除は、同じ年に支払ったものであれば、同時に申請することが可能です。
具体的には、確定申告を行う際に、寄付金控除と医療費控除をそれぞれ申請し、税務署に申告することができます。
3. 控除額の合算
寄付金控除と医療費控除は、個別に控除額が計算され、申告後にそれぞれ税額控除が適用されます。
つまり、両方を申請することで、総額の控除を増やし、最終的に払うべき税金を減らすことが可能です。
4. 申請方法の違い
医療費控除
医療費控除を申請するためには、医療費の領収書を基に支出金額を集計し、確定申告を行います。
寄付金控除
寄付金控除を申請するためには、寄付先から発行される「寄付金受領証明書」を基に申告を行います。また、寄付先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度を利用して確定申告なしで控除を受けることもできます。
5. 注意点
寄付金控除と医療費控除の併用において注意すべき点は、次の通りです。
申告の際の必要書類
両方の控除を申請する場合、必要な書類(医療費の領収書や寄付金受領証明書)を準備し、確定申告を正確に行うことが大切です。
自己負担額の調整
寄付金控除と医療費控除の両方を最大限活用するためには、それぞれの控除対象となる金額を把握し、年収や所得に応じた上限額を確認する必要があります。
6. ポイント解説

以下に、1~5のポイントをまとめました。
・寄付金控除と医療費控除は別々の控除ですが、同一の年度に両方を申請することができます。
・両者を併用することで、税金を軽減する効果を高めることができます。
・確定申告時には、必要書類をしっかり準備し、正確に申告することが大切です。
寄付金控除と生命保険料控除の併用
生命保険料控除は、生命保険の契約者が支払った保険料に対する税制優遇措置です。
この章では、寄付金控除と生命保険料控除を併用する際のポイントについて詳しく見ていきます。
生命保険料控除と寄付金控除の違い:6つのポイント
寄付金控除と生命保険料控除の違いについて、以下6つのポイントでご説明します。
1. 対象となる支出
生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料など、主に自身や家族のために支払った保険料が対象。
寄付金控除
特定の団体や自治体への寄付金(例:ふるさと納税や認定NPO法人への寄付)が対象。
2. 控除の種類
生命保険料控除
所得控除。支払った保険料の金額に応じて所得金額から控除され、その結果、課税される所得が減少。
寄付金控除
所得控除または税額控除の形で適用。
3. 控除額の上限
生命保険料控除
控除額には上限があり、最大で12万円(新制度の場合)。
寄付金控除
控除対象となる寄付金額は、寄付額から2,000円を差し引いた額が対象となり、上限額は寄付先や所得によって異なる。
4. 目的
生命保険料控除
自身や家族の生命や健康に対する保障を目的としており、主に個人の福利厚生に関連。
寄付金控除
公益活動や社会貢献に対する支援を目的としており、社会全体への貢献を促進。
5. 申請方法
生命保険料控除
確定申告時に、保険会社から送付される「控除証明書」を提出する必要があり、年末調整でも適用される。
寄付金控除
寄付先から発行された「寄付金受領証明書」を確定申告時に提出する。
6. 控除の対象期間
生命保険料控除
保険契約に基づく支払が対象となり、長期的に継続的な支出が前提となる。
寄付金控除
一回限りの寄付が対象となり、寄付を行った年のみに適用される。
お金の見直しを気軽に相談できるサイト
・家計見直しに特化したFP無料相談
寄付金控除と住宅ローン控除の併用
寄付金控除と住宅ローン控除は、それぞれ異なる税制優遇措置であり、併用することが可能です。
最後に、寄付金控除と住宅ローン控除を併用する際のポイントについて解説します。
住宅ローン控除と生命保険料控除の違い:6つのポイント
寄付金控除と住宅ローン控除の併用について、6つのポイントで整理すると、以下のようになります。
1. 対象となる支出
住宅ローン控除
住宅の購入、改築、リフォームなどに関連するローンの年末残高が対象
寄付金控除
特定の団体や自治体(例:ふるさと納税、認定NPO法人など)への寄付金が対象。
2. 控除の種類
住宅ローン控除
所得税の税額控除。住宅ローンの年末残高に基づいて控除額が計算されます。
寄付金控除
所得控除または税額控除の形で適用されます。
3. 併用の可否
寄付金控除と住宅ローン控除は、基本的には同時に適用可能です。
それぞれ異なる税制優遇を受けることができるため、併用することで税負担の軽減が期待できます。
4. 控除額の上限
住宅ローン控除
控除額はローンの年末残高に応じて決まります。(控除対象となる住宅の取得年などにより異なる)。
寄付金控除
寄付金額から2,000円を引いた額が控除対象(上限額あり)。
5. 申請方法
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、初年度に確定申告が必要ですが、その後は年末調整で適用されることが一般的です。
寄付金控除
寄付金受領証明書を提出し、確定申告が必要です(ふるさと納税の場合はワンストップ特例も可)。
6. 控除の対象期間
住宅ローン控除
住宅ローンを借り入れている期間、最大10年間(住宅によって異なる)継続的に適用されます。
寄付金控除
寄付を行った年に限り控除が適用されます。

控除は、納税者が税負担を軽減できる制度です。
その他の控除についても、しっかり学んでおきましょう。
参照サイト
・配偶者控除と扶養控除の併用による節税効果
・寄付金控除を活用しよう!6つの控除対象となる寄付先の解説
まとめ
今回の記事のまとめです。
寄付金控除は、医療費控除や生命保険料控除、住宅ローン控除などと併用できます。
これにより、所得税の軽減が期待できます。
ただし、各控除には適用条件があるため、控除に関する正しい知識を持つことが大切です。