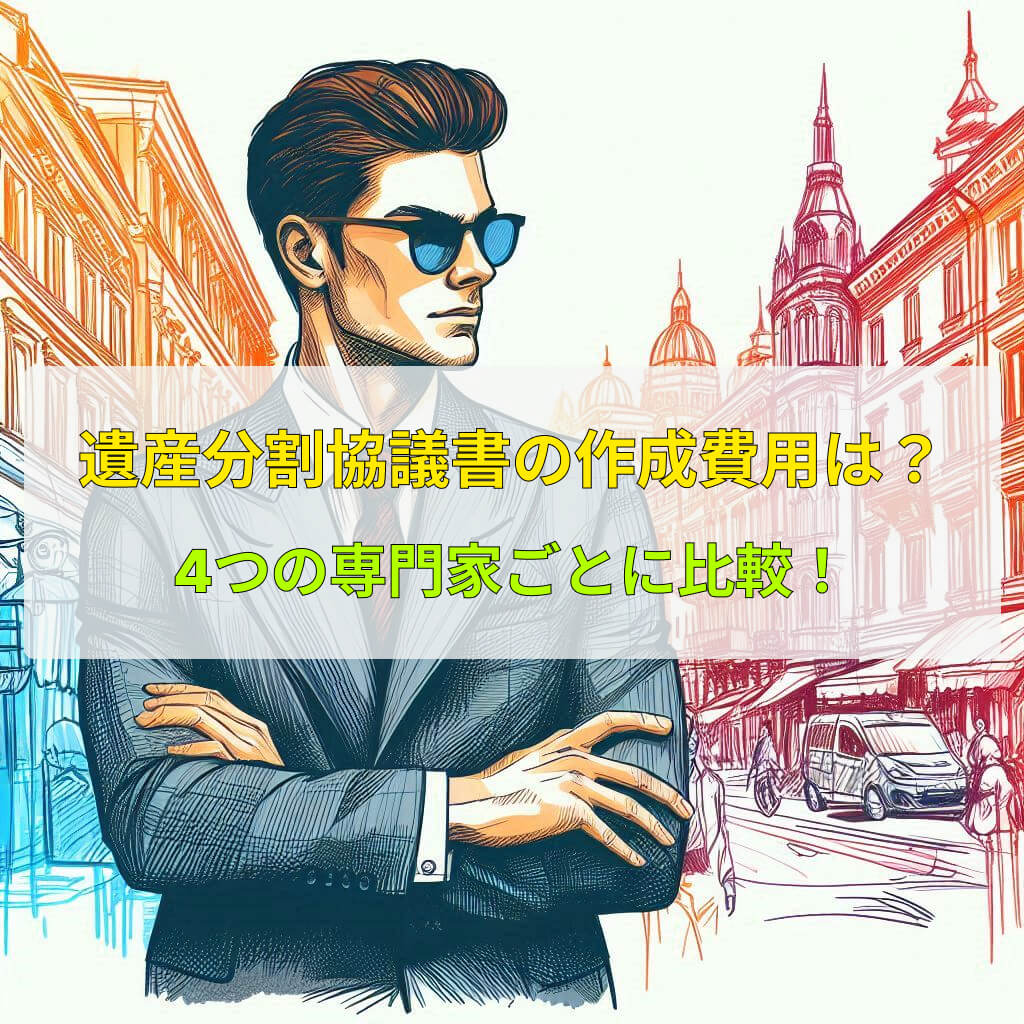相続は、財産を次の世代に引き継ぐ重要な手続きですが、時に想定外の事態が発生することもあります。
その一つが「代襲相続」です。
代襲相続とは、相続人が先に亡くなっていた場合に、亡くなった相続人の子ども(代襲相続人)がその役割を引き継ぐ制度です。
特に、家族構成や相続人の状況によって、代襲相続がどのように発生するのかを理解しておくことは、円滑な相続手続きに欠かせません。
この記事では、代襲相続の基本的な概念から発生するケース、そしてスムーズに手続きを進めるためのポイントを詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 代襲相続の基本的な概要
- 代襲相続が行えるケースと行えないケース
- 代襲相続の手続き方法

代襲相続の際に、できること・できないことについて学んでいきましょう。
代襲相続の基本概念とは
代襲相続は、相続人に代わって相続を行う制度ですが、代襲相続人が相続できる場合とできない場合があります。
まずは、代襲相続の基本的な概要を理解しておきましょう。

基本的な3つの相続方法については、以下のコラムをご参照ください。
そもそも、代襲相続って?
代襲相続とは、相続人が本来相続を受けるべき立場にあったものの、被相続人が亡くなる前にその相続人が死亡したり、相続権を失った場合に、その相続人の子どもが代わりに相続を受ける制度です。
具体的には、相続人が死亡したり、相続人の相続権が欠陥した場合、その相続人の子ども(代襲相続人)が財産を引き継ぐことができます。
ただし、代襲相続が成立するためには一定の条件があり、必ずしも自動的に認められるわけではありません。

代襲相続人は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)または、死亡した兄弟姉妹の子に該当します。
代襲相続が適用される場合とは
代襲相続が適用される場合は、主に以下3つの条件が満たされた時などです。
①相続人が先に死亡した場合
本来相続するはずだった相続人が先に亡くなっている場合、その相続人の子ども(代襲相続人)が代わりに相続します。
例:父親が亡くなった時にその子がすでに亡くなっている場合など
②相続人の相続権が廃除された場合
相続人が法的に相続権を失った場合、代襲相続が適用されます。
例:相続人が犯罪を犯し、裁判所により相続権が廃除された場合など
③相続人の相続権が失権・欠陥した場合
相続人が法的に相続権を失う場合、代襲相続が適用されます。
例:遺留分を侵害する行為をした場合などが該当します。

また、養子縁組をした子どもも、養親の直系血族となり、代襲相続人となります。
参照サイト
・法務局『主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例』
代襲相続の相続にならない4つのケース
一方で、代襲相続が発生しないケースには、以下の4つが挙げられます。
1. 相続人が相続放棄した場合
相続人が相続放棄をすると、その相続権は最初から存在せず、代襲相続も発生しません。
2. 配偶者は代襲相続の対象外
代襲相続の対象には配偶者は含まれません。代襲相続人になるのは、被相続人の子どもや兄弟姉妹など、直系卑属のみです。
3. 兄弟姉妹の子どもは代襲相続できるが、その子どもは対象外
兄弟姉妹が亡くなった場合、その子どもは代襲相続を行いますが、さらにその子どもの子どもは代襲相続権を持ちません。
4. 遺言書の内容は代襲相続されない
遺言書に記載された内容は、代襲相続人には適用されません。代襲相続は、法定相続人の権利に基づいて行われます。
相続について相談できるサイト
・相続に強い税理士紹介
代襲相続の手続き方法
代襲相続が発生した場合、通常の相続手続きとは異なることがあります。
次に、この章では、代襲相続の手続き方法について詳しく見ていきましょう。
代襲相続に必要な書類
代襲相続に必要な書類は、主に以下の8つが挙げられます。
①登記申請書
不動産相続に必要な申請書。
②遺産分割協議書
相続人全員が遺産の分割方法に合意した内容を記載した書類。
③相続人の印鑑登録証明書
相続人の印鑑を証明する書類。
④相続人の住民票
相続人の住所を確認するための書類。
⑤被相続人の住民票(除票)および戸籍謄本
被相続人の死亡や身分を証明する書類。
⑥被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本
代襲相続人が代襲相続する権利があることを確認するための書類。
⑦固定資産評価証明書
相続する不動産の評価額を証明する書類。
⑧相続関係説明図
相続人の関係を図式化した書類。
代襲相続が完了するまでの5つのステップ
代襲相続の流れは、以下の5つのステップで進められます。
①代襲相続人の確定
相続人を確定する必要があり、被代襲者の直系卑属(子や孫)、または被代襲者が兄弟姉妹の場合はその子が代襲相続人となります。
②必要書類の準備
代襲相続を行うために、被相続人や被代襲者の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続関係説明図などを準備します。
③遺産分割協議の実施
代襲相続人を含む相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意の上で遺産分割協議書を作成します。
④相続手続きの実施
銀行の相続手続きや不動産の相続登記、必要に応じて相続税の申告を行います。
⑤代襲相続の完了
すべての手続きが完了すると、代襲相続による財産の承継が正式に確定します。

※指定された相続人が亡くなっている場合(遺言による場合)、遺言は無効となり、代襲相続は発生しないため、必要書類は通常の相続と同じになります。
相続について相談できるサイト
・相続税に特化したFP無料相談
代襲相続をスムーズに進めるためのポイント
必要書類や手続き方法については先ほどの章で解説しましたが、最後に、代襲相続をスムーズに進めるためのポイントや注意点について確認していきます。
代襲相続について起こりやすい3つのトラブル事例
代襲相続は、遺産分割や法的手続きの際にトラブルが発生しやすいため、十分な注意が必要です。
以下に、代襲相続で起こりやすい3つのトラブル事例を挙げてみます。
①相続人間で遺産の評価額に対する意見の食い違い
代襲相続人は、相続する遺産の評価額に関して、意見が分かれることがあります。
例えば、不動産の評価額や株式、貴金属などの資産について、適切な評価方法に合意できず、相続人同士で対立が生じることがあります。
このような意見の食い違いは、相続手続きの遅延や追加の費用を引き起こす原因になります。
②代襲相続人の存在に関する認識の違い
代襲相続人が遺産相続に関与する場合、事前にその存在を認識していない場合があります。
例えば、代襲相続人が相続人の中に含まれていないと誤解している場合や、代襲相続人が遺言書に記載されていない場合、手続きの途中で新たに相続人として認められることがあるため、他の相続人と意見が分かれることがあります。
③遠方に住む代襲相続人との連絡が取れない
遠方に住んでいる代襲相続人と連絡が取れない場合、遺産分割協議に参加できない可能性があります。
この場合、代襲相続人が協議に出席しないことによって、手続きが遅延したり、協議の合意に時間がかかることがあります。
さらに、連絡が取れない代襲相続人が後に現れた場合、遺産分割が無効となる可能性があるため、注意が必要です。
相続のことは誰に相談すればいい?
相続時には、相続人に関する問題をはじめ、相続財産の評価額の算出など、さまざまな課題が生じます。
その中でも最も頭を悩ませるのが、相続税をはじめとする税金の問題です。
税理士に相続に関する相談をするメリット
相続時に税理士に依頼するメリットは、税理士の専門知識を活かして、相続時の手続きをスムーズに進められる点です。
具体的には、以下4つのメリットがあります。
①相続税の計算と申告
相続税の計算は複雑で、誤った申告をすると追徴課税のリスクがありますが、相続財産の適正評価と適切な税務申告をサポートします。
②節税対策の提案
相続税の負担を軽減するために、生前贈与や不動産の評価額の適正化など、具体的な節税策を提案します。
③相続税納付方法の提案
相続税が多額になる場合、分割納付や物納などの納付方法を通じて、納税負担を軽減する方法を提案ます。
④遺産分割協議のサポート
複数の相続人がいる場合、遺産分割を巡る対立が生じることがありますが、公平な分割ができるようにサポートします。

遠方だと税理士に相談できないと思っていませんか?
実は、リモートで税理士に相談できるサービスもありますよ!
近場の税理士が見つかるサイト
・近場の税理士を探すなら、税理士紹介ネットワークへ
まとめ
今回の記事のまとめです。
代襲相続は、相続人が先に亡くなったり、相続権を失った場合、その相続人の子どもが代わりに相続を受ける制度です。
相続権が廃除されたり、失権した場合にも代襲相続が適用されますが、一定の条件があるため、専門家のアドバイスを受けることも大切です。