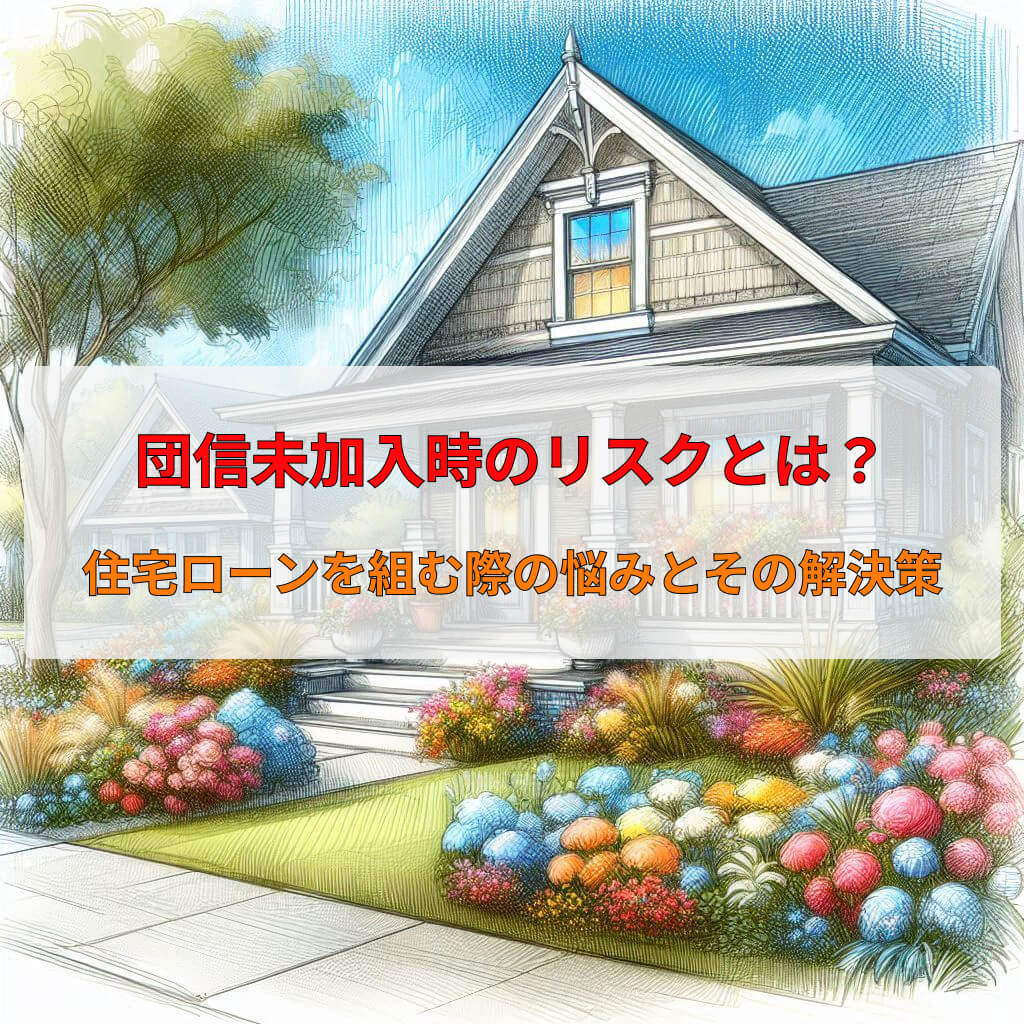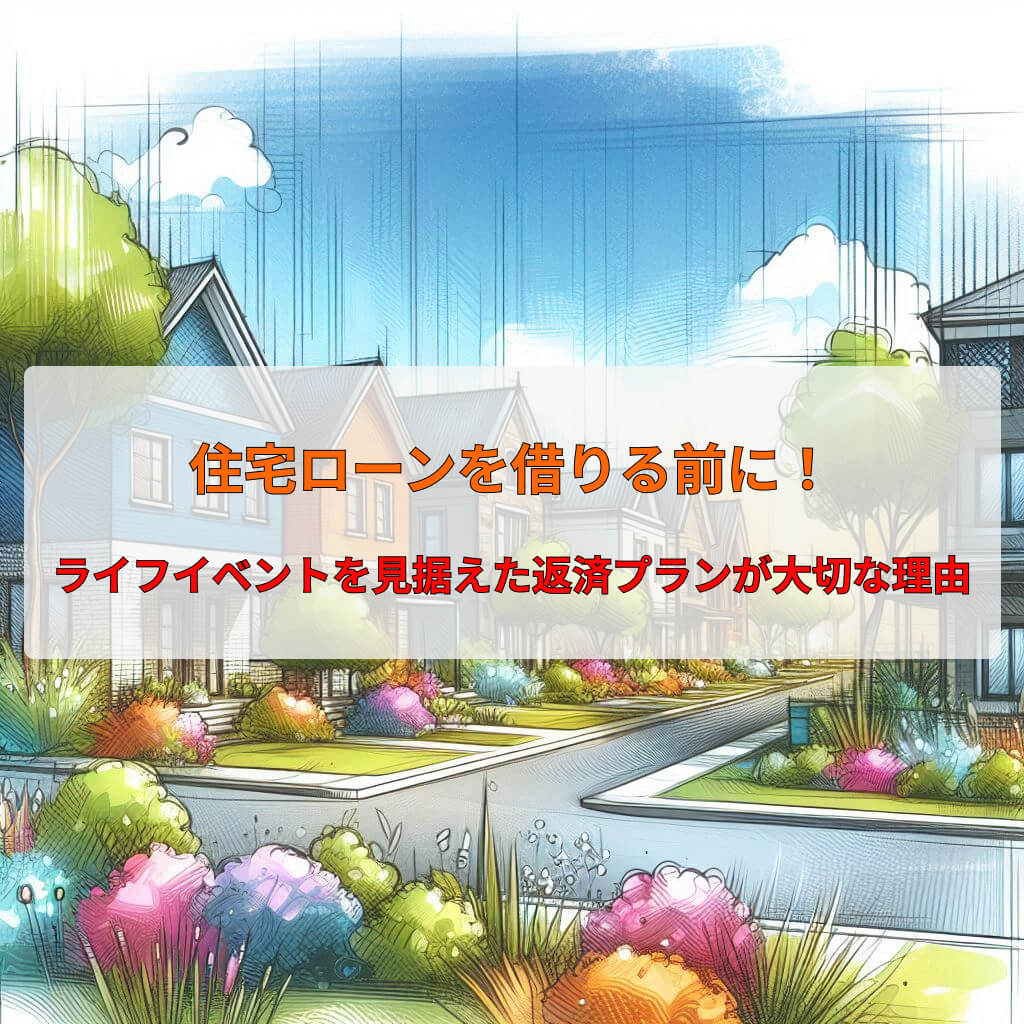『団信に加入しない場合にはどうなるの?』
住宅ローンを組む際、団体信用生命保険(団信)への加入を勧められることがありますよね。
この保険は、万が一の事態に備えるためのものですが、
実際には加入しないという選択肢もあります。
本記事では、団信に加入しないことによるリスクやその対策、さらに住宅ローンを組む際の悩みについて詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- 団体信用生命保険に未加入の場合のリスク
- 団体信用生命保険以外のリスクヘッジとは?
- 住宅ローンを組む際の悩みとその解決法

団信に加入しない場合のリスクをどうカバーするか、一緒に考えてみましょう。
団体信用生命保険に加入しないリスクとは?
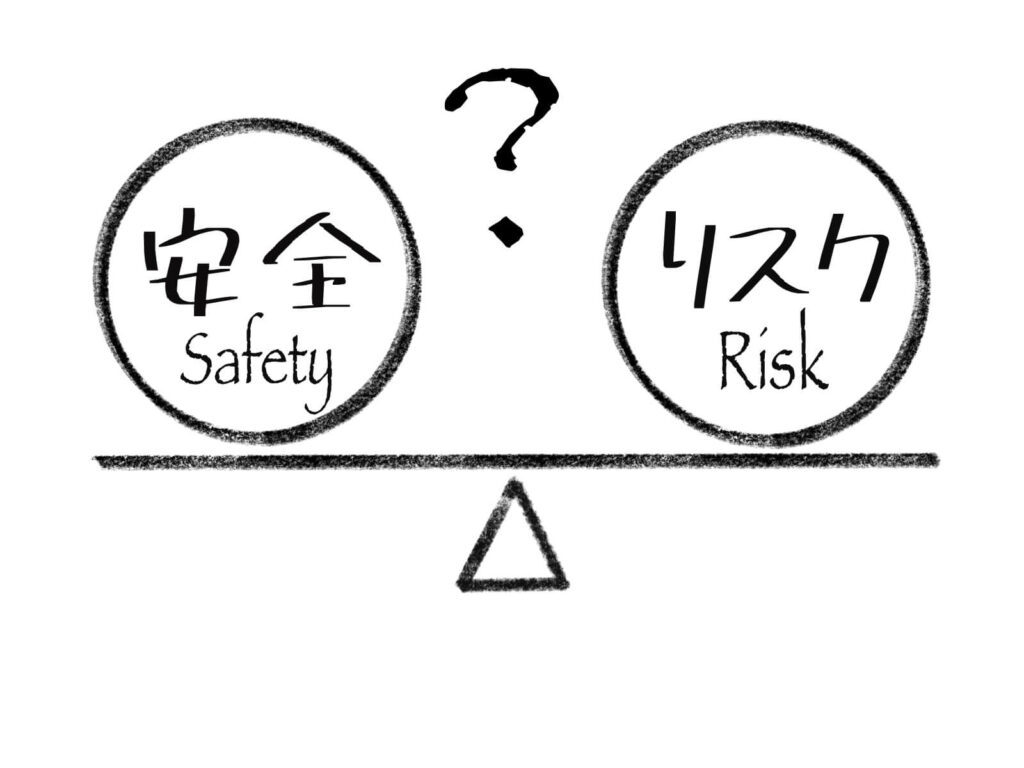
団体信用生命保険(団信)とは、主に住宅ローンを利用する際に加入する保険で、借入者が死亡または高度障害に陥った場合に、残りのローン残高を保険金で支払う仕組みです。
まず最初に、団体信用生命保険に加入しない場合に起こりうるリスクについて見ていきます。

団体信用生命保険(団信)の概要については、以下のコラムでわかりやすくまとめていますよ!
参照コラム
・団体信用生命保険の基礎知識|住宅ローン残債がゼロになる仕組み解説
借入者の死亡リスクとその影響
一般的な団体信用生命保険(団信)は、契約者が死亡したり所定の高度障害状態になった場合に、住宅ローンの残高がゼロになります。
つまり、借入者が亡くなった際、住宅ローンは家族に引き継がれますが、団信に加入していれば、死亡時に保険金が支払われてローンが完済されるため、家族は経済的な負担を軽減できます。

借入者が死亡した際には、以下の3つのような経済的影響が考えられます。
①ローンの返済負担
家族は残されたローンを返済しなければならず、毎月の支出が増加します。
➁生活水準の低下
収入源が失われるため、家族の生活水準が低下する可能性があります。
③財産の喪失
住宅が手放されることになれば、家族が長年住んできた場所を失うことになります。
家族の経済的負担が増える可能性
団体信用生命保険(団信)に加入しないリスクの一つは、万が一の事態が発生した場合に、家族の経済的負担が増える可能性があることです。

具体的には、以下の3点が考えられます。
①住宅ローンの残高が家族に残る
借入者が死亡した場合、住宅ローンの残高が家族に引き継がれ、返済義務が生じて生活が圧迫されることがあります。
➁収入の喪失
借入者が亡くなると、その収入がなくなり、家族は生活費や教育費の支払いに困難を感じ、負担が増す可能性があります。
③返済ストレスと生活水準の低下
家族は住宅ローンの返済で経済的に厳しくなり、生活費や教育費を削減せざるを得ず、精神的な負担が増す可能性があります。
保険に関する相談ができるサイト
・【みらいのほけん】公式
団体信用生命保険以外のリスクヘッジとは?

前章で述べたように、団信に加入することで万が一のリスクに備えることができます。
しかし、団信だけでなく、他にもさまざまなリスクヘッジの方法があります。

この章では、団体信用生命保険以外のリスクヘッジ方法について確認していきましょう。
住宅ローンや住宅購入に悩んでいる方へ
・みんなの生命保険アドバイザーは全国相談無料!
団体信用生命保険以外の4つのリスクヘッジ方法
団体信用生命保険(団信)以外のリスクヘッジ方法には、以下4つの選択肢などがあります。

万が一の際に役立つ、収入確保のための4つの保険タイプのご紹介です。
1. 個人生命保険
概要
団信と同様に、死亡や高度障害時に保険金が支払われる個人型生命保険。
メリット
より柔軟な保障内容を選べるため、自身のライフスタイルやニーズに応じた保険が設定可能。
生命保険に関するコラム
・生命保険(第一分野の保険)についての解説|3つの保険タイプの違いとは?
2. 収入保障保険
概要
借入者が死亡または高度障害になった場合に、定期的に保険金が支払われる保険。
メリット
収入が途絶えた場合でも、生活費やローン返済が継続的に支払われるため、家計への影響を軽減できる。
収入保障保険に関するコラム
・収入保障保険を活用したリスクマネジメント
3. 就業不能保険
概要
怪我や病気で就業不能になった場合に給付金が支払われる保険。
メリット
自身の仕事に特化したリスクに備え、就業不能期間中の収入途絶による負担を軽減できる。
就業不能保険に関するコラム
・就業不能保険で備えるべきリスクとは?
4.学資保険
概要
子どもの教育資金を積み立てるための保険で、万が一の場合でも、教育資金が保証される。
メリット
教育資金を準備できるだけでなく、万が一の際には保険料が免除され、給付金を受け取れる保障がある。
学資保険に関するコラム
・学資保険のメリットとデメリット、教育資金準備方法を総まとめ

各保険が、どのような場面で役立つかを把握しておくことが大切ですね!
住宅ローンを組む際の悩みとその解決策

住宅ローンを組むときは、自己資金をはじめとしたさまざまな悩みが生じます。

最後に、その悩みと解決策について確認しておきましょう。
自己資金はどのくらい必要なの?
頭金の金額や自己資金の有無が住宅ローンの審査に大きな影響を与えるため、自己資金をどのくらい準備すべきか悩むことがよくあります。
一般的には、物件価格の20%程度を頭金として用意することが望ましいとされていますが、実際のところは個々の状況によって異なります。
ただし、自己資金が少ないと、金融機関からの信頼が低くなり、審査に通りづらくなることがあります。
さらに、頭金が少ない場合は、借入額が増えるため、将来的な返済負担が重くなり、生活設計にも影響を及ぼします。
そのため、自己資金を計画的に貯蓄することや、贈与を受ける方法など、さまざまな選択肢を検討することが大切です。
あわせて読みたいコラム
・住宅ローン前に!ライフイベントを見据えた返済プランが大切な理由
固定金利と変動金利はどちらがお得なの?
住宅ローンの返済額に大きく影響する要素として、金利が挙げられます。
特に、固定金利と変動金利の選択は多くの人にとって悩ましいポイントです。
固定金利は契約時の金利が返済期間中ずっと適用されるため、将来的な返済計画が立てやすい一方、
変動金利は市場金利の影響を受けやすく、将来的に金利が下がると、返済額が減少する可能性があります。
そのため、変動金利を選ぶ際は、将来的な生活費やライフスタイルの変化を考慮した選択が必要となります。
合わせて読みたいコラム
・市場金利が住宅ローンに与える影響とは?固定・変動金利の判断基準
住宅ローンの審査における健康状態の影響とは?
住宅ローンの審査では、加入者の健康状態が審査に影響を及ぼすことがあります。
特に、団体信用生命保険(団信)への加入が求められる場合、健康状態が審査基準の一つとなります。
現在持病がある場合や、過去に大きな病歴がある場合、団信への加入が難しくなることがあります。
そのため、健康状態に不安がある場合は、事前に専門医の意見を仰いだり、保険会社に相談することが有効な対策となります。
住宅ローンや住宅購入に悩んでいる方へ
・みんなの生命保険アドバイザーは全国相談無料!
まとめ
今回の記事のまとめです。
団信に加入しない場合、以下3つの経済的リスクが考えられます。
- ローンの返済負担が残る
- 生活水準が低下する可能性
- 財産の喪失
これらのリスクに備えるためには、団体信用生命保険以外にもさまざまなリスクヘッジ方法があります。
例えば、個人生命保険、収入保障保険、就業不能保険、学資保険などが挙げられ、これらの保険を活用することで、万が一の際に備えることができます。