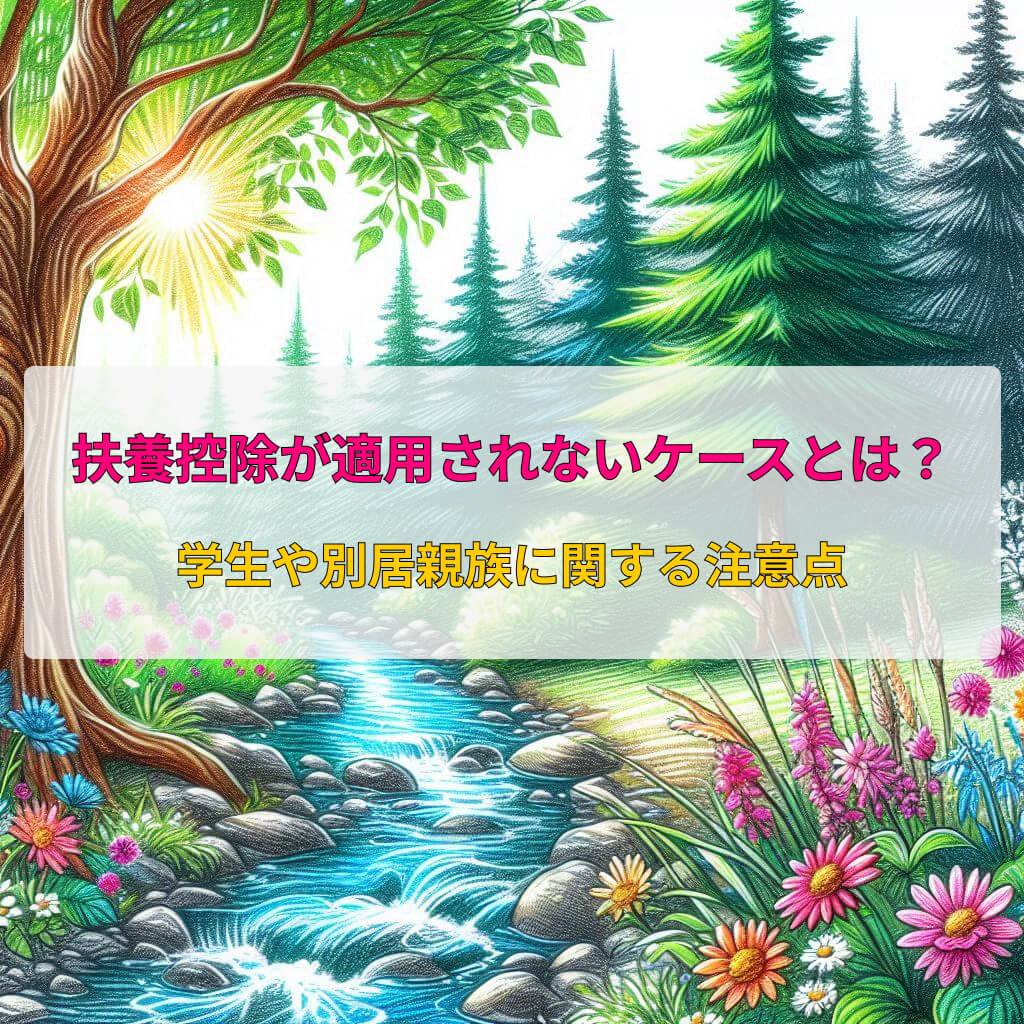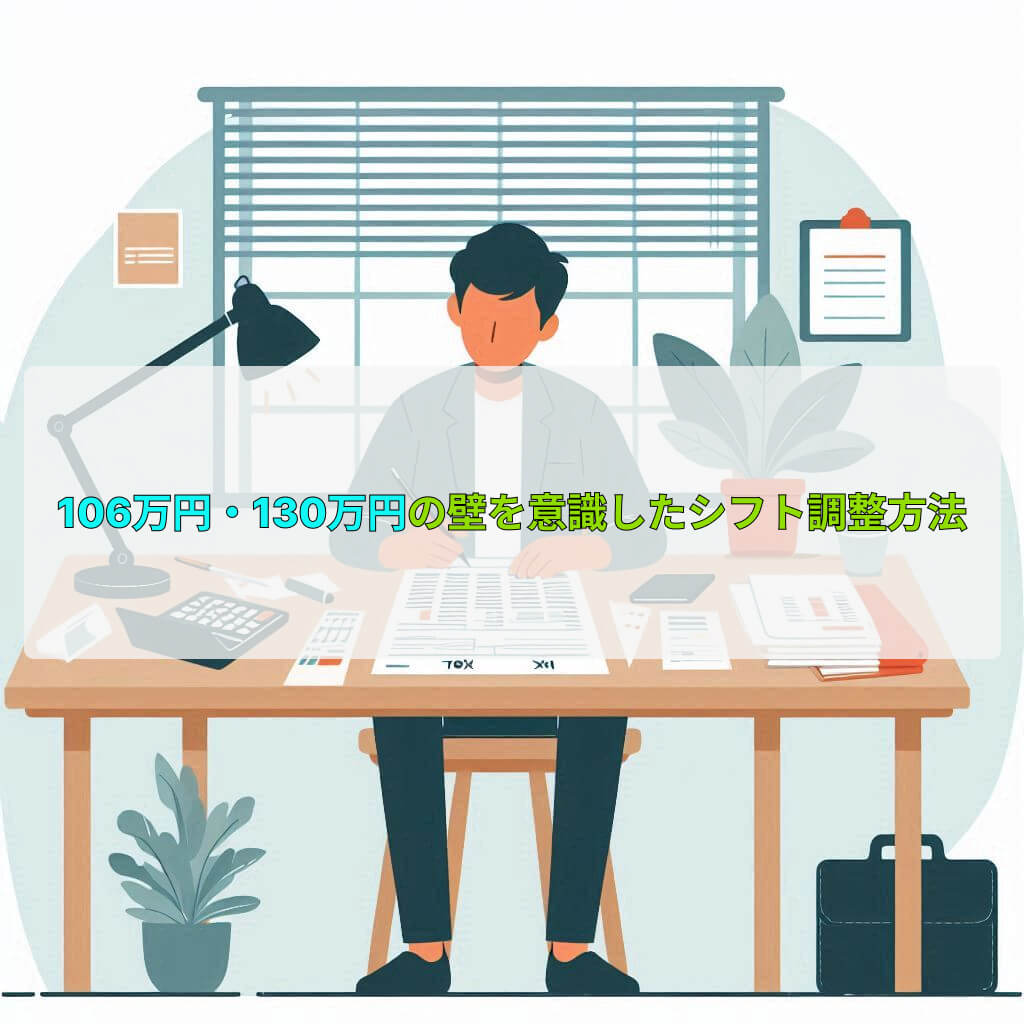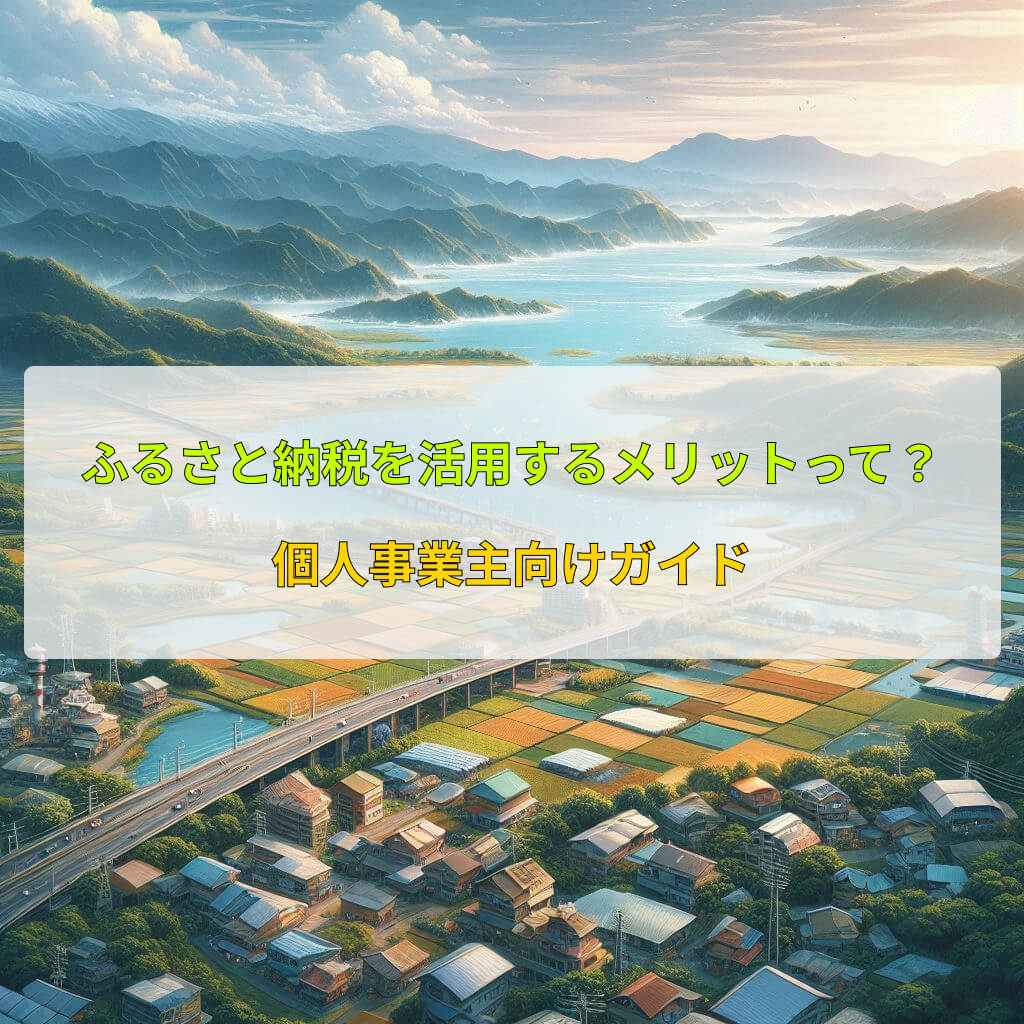『扶養控除の対象範囲って?』
扶養控除は、家庭の状況に応じて税金を軽減できる公的制度ですが、その対象者や条件を正しく理解していないと、節税効果を最大限に活用することができません。
たとえば、「別居している家族は扶養控除の対象になるのか?」というのは、よくある疑問の一つかもしれません。
本記事では、扶養控除の基本的な仕組みから応用的な活用方法まで、知っておくべきポイントについてわかりやすく解説していきます。
この記事で分かること
- 扶養控除の基本
- 扶養控除が適用される対象者の条件
- 扶養控除を受けるための手続き

扶養控除が適用される対象者の条件について、詳しく解説していきます。
扶養控除の知っておきたい基礎情報
いきなりですが、扶養控除の対象者の年齢って何歳からかご存知でしょうか?
まずは、扶養控除の基本的な概要を確認してみましょう。
扶養控除の基本的な仕組み
扶養控除とは、納税者が扶養している家族(主に子どもや親、配偶者など)を控除対象として、その分税額を軽減できる制度です。
具体的には、扶養親族が一定の条件を満たすと、納税者の所得から一定額が差し引かれ、その結果税額が軽減されます。

ただし、扶養控除を受けるためには、以下3つの条件等を満たす必要がありますよ!
①年齢条件
扶養親族は16歳以上であることが必要ですが、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)については控除額が増額されます。
➁収入条件
扶養される側の年間所得が48万円以下で、給与所得者は年収103万円以下である必要があります。
③生活の実態
扶養親族が扶養者から生活費を受けていれば、別居していても扶養控除が適用される場合があります。
扶養控除に関するサイト
・No.1180 扶養控除|国税庁
扶養控除のメリット
扶養控除にはさまざまなメリットがありますが、特に、税額の軽減によって家計の負担が軽くなることが大きな利点です。
以下に、扶養控除の主なメリットを3つ解説します。
1. 家計の経済的負担を軽減できる
扶養控除によって税額が減ることで、特に扶養家族が多い家庭や子どもの進学を控えた家庭にとって、大きなサポートとなります。
2. 家庭状況に応じた適切な支援が受けられる
納税者の家庭状況に応じた税制支援により、家族の人数や扶養家族の条件(例:特定扶養親族や高齢者)に応じて控除額が増加します。
3. 他の控除との併用ができる
扶養控除は、医療費控除や住宅ローン控除、生命保険料控除など他の税制優遇措置と併用することで、さらに税金の軽減が可能となります。

医療費控除や住宅ローン控除など、その他の控除については、以下のコラムをご参照ください。
参照コラム
・医療費控除の適応範囲と活用|個人事業主の確定申告
・住宅ローン控除とは?仕組みと手続き方法をわかりやすく解説!
扶養控除が適用される対象者の条件とは?
先ほど少し触れましたが、扶養控除には適用条件があるため、その対象条件をしっかり理解することが大切です。
この章では、扶養控除が適用される対象者の条件について、さらに詳しく見ていきましょう。
扶養控除の対象条件
扶養控除の対象条件について、以下5つのポイントをおさえておきましょう。

扶養控除は、基本的に納税者が扶養している親族に適用されます。
1. 対象となる親族
扶養控除の対象となる親族は、6親等以内の血族および3親等以内の姻族に限られます。

6親等以内の血族および3親等以内の姻族に該当する親族は、以下の通りです。
・配偶者
・子ども
・父母
・兄弟姉妹
・祖父母
・義父母(同居していることが必須) など
2. 年齢制限
扶養控除を受けるには、年齢制限があります。
特に16歳以上の親族が対象となるため、子どもに関しては16歳未満の場合、扶養控除の対象外です。
また、19歳以上の子どもについては、特別控除(特定扶養控除)が適用されることもあります。

ちなみに、15歳以下の子どもは扶養控除ではなく、児童手当の対象となります。
児童手当に関するコラム
・児童手当の拡充とは?第三子以降の給付金額について
3. 扶養の実態
扶養控除の対象として認められるためには、扶養親族が納税者の家計に依存していることが必要です。
例えば、親族が独立して自分で生計を立てている場合や、年収が一定額を超えている場合(例えば、年収103万円以上など)は、扶養控除の対象外になります。
4. 特定扶養親族(高齢者や障害者)
扶養控除は、特定の親族に対して追加の控除額が適用される場合があります。
例えば、高齢者(70歳以上)や障害者が扶養親族に該当する場合、年齢や障害の有無によって、扶養控除が増額されることがあります。
5. 住居が別の場合でも扶養対象
扶養親族が別居している場合でも、家計の支援が継続して行われていれば、扶養控除の対象となります。
ただし、別居親族が自分で生計を立てている場合は扶養控除が適用されない場合もあるので注意が必要です。
扶養控除の対象者別チェックポイント
扶養控除のポイントの一つは、年齢によって適用される制度が異なることです。

以下に、扶養親族の年齢別に適用される公的制度をまとめてみます。
チェックポイント
・16歳未満の子どもは「児童手当」の対象
・16歳以上19歳未満(高校生)は「一般扶養控除」の対象
・19歳以上23歳未満(大学生相当)は「特定扶養控除」の対象
・70歳以上の親族(同居・非同居問わず)は「老人扶養控除」の対象
扶養控除に関するサイト
・No.1180 扶養控除|国税庁
扶養控除が適用されないケース|学生や別居の親族
扶養控除は、すべての親族に対して適用されるわけではありません。
最後に、扶養控除が適用されないケースについて、いくつかの注意点を見ていきましょう。
学生でも扶養控除が適用されない場合
扶養親族として認められるためには、一定の収入条件を満たす必要があります。
特に学生については、以下2つのようなケースで扶養控除が適用されないことがあります。
①年間の合計所得が48万円を超える場合(給与収入ベースで年収103万円以上)
アルバイトなどで年間の収入が一定額を超えた場合、その学生は扶養親族として認められないため、親の扶養控除から外れます。
➁仕送りが不足している場合
学生が別居している場合でも、親が生活費の大部分を負担していないと、扶養控除が適用されないことがあります。
別居の親族が扶養控除の対象外になるケース
別居している親族も扶養控除の対象になり得ますが、いくつかの条件があります。
以下3つのような場合、扶養控除が適用されないことがあります。
①年間の合計所得が48万円を超える場合
別居している親族(例:両親)の年間所得が48万円を超えると、扶養控除の対象外となり、特に年金収入がある場合は雑所得としてカウントされるため注意が必要です。
➁経済的援助が不十分な場合
別居している親族が親からの経済的援助を受けていない、または援助額が少ない場合、その親族は扶養親族として認められない場合があります。
③親族が他の人の扶養に入っている場合
例えば、別居している親族が兄弟姉妹の扶養に入っている場合、その親族を同時に扶養控除の対象にすることはできません。

扶養控除の適用条件は少し複雑ですので、詳しくはFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのもおすすめです。
FPに無料相談できるサイト
・FP無料相談の保険チャンネル
青色専従者として青色専従者給与を受給している場合
青色専従者給与を受けている親族は、扶養控除の対象にはなりません。
これは、青色専従者として給与を受け取ることで、既に所得を得ていると見なされるからです。
具体的には、次のような理由が挙げられます。
①所得が発生しているため
青色専従者給与を受け取ると、その家族は事業主の扶養親族ではなく従業員として扱われ、年間48万円以上の所得がある場合、扶養控除の対象外となります。
➁事業専従者控除が優先される
青色専従者として支払った給与は経費として計上されるため、同じ家族に扶養控除を併用することはできません。

扶養控除は、他の控除と併用することで節税効果がさらに高まります。
参照コラム
・配偶者控除×扶養控除でできる節税術
まとめ
今回の記事のまとめです。
扶養控除は、納税者が扶養する親族に対して税額を軽減する制度で、16歳以上で年間所得48万円以下(給与所得者は年収103万円未満)が対象となります。
別居していても、扶養者からの経済的支援が大半を占めている場合は対象となりますが、青色専従者や年収103万円を超える学生は扶養控除の対象外となります。