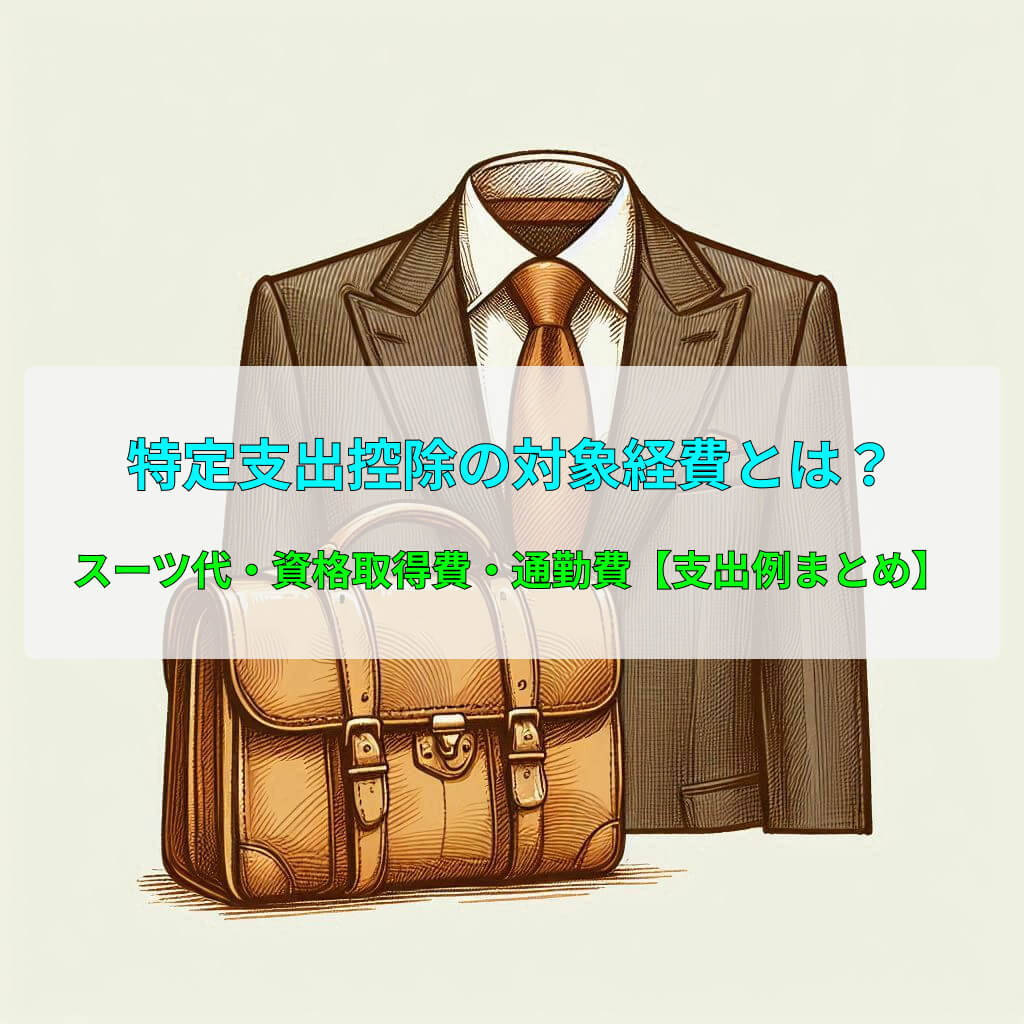『配偶者控除っていくらなの?』
配偶者控除は、家庭の税負担を軽減するための公的制度ですが、適用される所得制限がいくらまでかご存知でしょうか?
配偶者控除を受けるには、一定の所得や収入条件を満たす必要があり、この所得制限を適切に活用することで、節税効果を最大化できます。
この記事では、配偶者控除の基本や所得制限の詳細、そしてその制限をクリアするための方法について解説していきます。
この記事で分かること
- 配偶者控除の仕組み
- 配偶者控除の所得制限の具体的な基準
- 所得制限をクリアするための方法

配偶者控除の適用条件などについて、一緒に学んでいきましょう。
配偶者控除の仕組み

配偶者控除は、配偶者が一定の要件を満たす場合に、納税者の税負担を軽減する税制上の制度です。
まずは、配偶者控除の仕組みについて見ていきましょう。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いについては、以下のコラムでまとめていますよ。
参照コラム
・私も控除対象になるの?配偶者特別控除の適用条件と申請手続きの解説
そもそも、配偶者控除とは?
そもそも、配偶者控除とは、配偶者の所得が一定の条件を満たす場合に、納税者(主に夫または妻)の税負担を軽減する制度です。
この控除を利用することで、納税額が減少し、家計への負担が軽減されるというメリットがあります。
ただし、配偶者の所得や年収に応じて控除額が変わる点が大きなポイントの一つです。

そのため、配偶者控除を受けるためには、配偶者の所得・年収が一定額以下である必要があります。
参照サイト
No.1191 配偶者控除|国税庁
所得制限とは?配偶者控除に与える影響
所得制限とは、税制において、特定の控除や支援を受けるために設けられた収入の上限を指します。
特に配偶者控除においては、配偶者の年収が一定額を超えると、控除が適用されなくなる、または控除額が減少するという制限があります。
つまり、配偶者控除を受けるためには、配偶者の年収が一定の上限(所得制限)を超えないことが必要です。
具体的には、配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除が適用されなくなるケースが一般的です。
これがいわゆる「年収103万円の壁」として広く認識されています。

年収103万円の壁については、以下のコラムで詳しく解説しています。
参照コラム
・パート収入103万円超えの落とし穴!定額減税の仕組みと併せて解説
配偶者控除の所得制限の具体的な基準
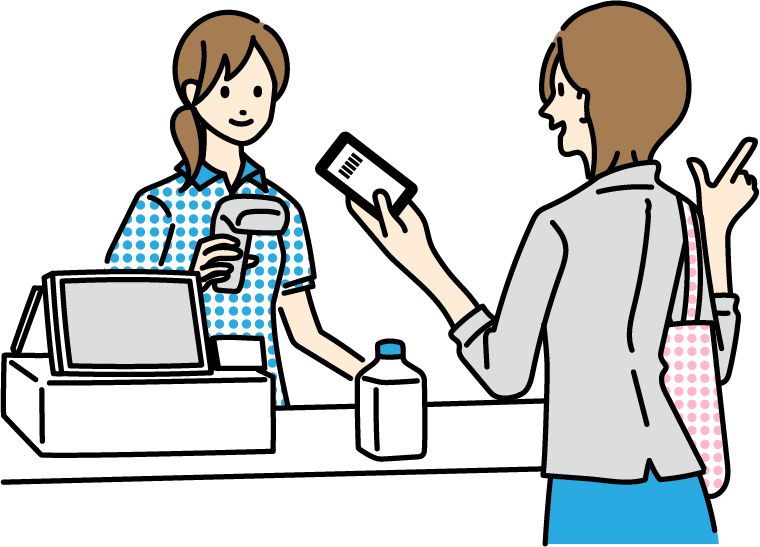
次に、配偶者控除の所得制限に関する具体的な基準を見ていきます。
先ほど触れたように、配偶者控除には適用される上限額が設定されていますが、この上限額は所得や給与収入に応じて異なります。

この章では、配偶者控除の所得制限に関する具体的な基準について詳しく見ていきます。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を適用するためには、主に以下4つの条件を満たす必要があります。
①民法上の配偶者であること
配偶者控除は、法律上の夫婦にのみ適用され、内縁関係や事実婚には適用されません。
➁納税者と生計を一にしていること
配偶者は、その年の12月31日時点で納税者と同一の家計で生活している必要があります。
③青色申告者の事業専従者でないこと
青色申告をしている場合、配偶者がその事業専従者として給与を受け取っていない、または白色申告者の専従者でないことが求められます。
④年間合計所得額が48万円以下であること
配偶者の年間合計所得が48万円以下、または給与収入のみの場合は年収103万円以下であれば、配偶者控除が適用されます。

④の条件については、次の章で詳しく解説していきます。
配偶者の収入制限額とは?
配偶者控除を受けるためには、配偶者の収入制限を満たす必要があります。
特に、給与収入のみの場合と、不労所得(株や不動産など)がある場合などで条件が異なります。

この制限は、①給与収入と②合計所得金額の2つの観点から考えることができます。
①給与収入が103万円以下であること
配偶者が一か所の事業所からパートとして給与収入を得ており、その収入が103万円以下であれば、給与収入のみの場合に配偶者控除を受けることができます。
➁年間の合計所得金額が48万円以下であること
配偶者が給与収入以外にも不労所得(例えば株の配当金や不動産収入など)を得ている場合、その年間の合計所得金額は48万円以下でなければなりません。

合計所得金額は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額に、不労所得やその他の所得を加えた総額となります。
納税者本人の合計所得金額に基づく控除金額
配偶者控除の適用条件についてはこれまでお話ししてきましたが、納税者本人にも適用条件が設けられています。

以下の図1では、納税者本人の所得に基づく控除額をまとめています。
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」より

なお、老人控除対象配偶者とは、配偶者が65歳以上である場合を指します。
FPに無料相談できるサイト
・【みらいのほけん】公式
所得制限をクリアするための方法:他の控除との併用
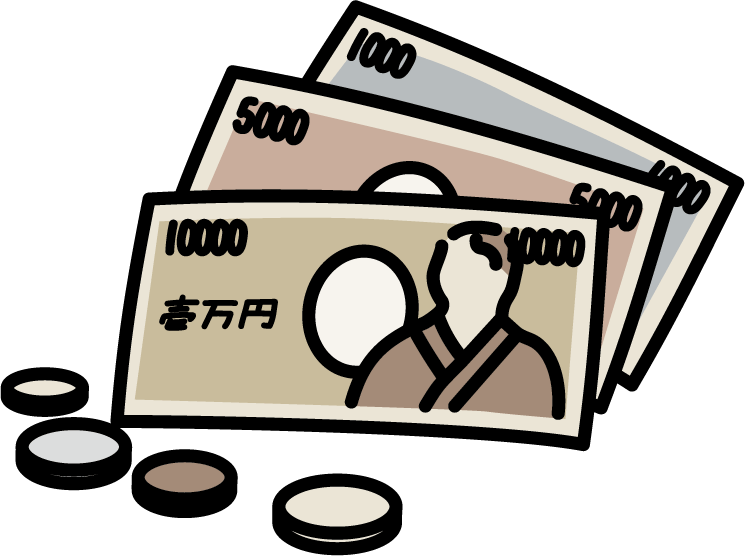
配偶者控除を適用するには、配偶者の年間合計所得が48万円以下、または給与収入のみの場合は年収103万円以下である必要があります。

最後に、所得制限をクリアするための方法を見ていきましょう。
収入が制限額を超えた場合の影響
収入が制限額を超えた場合の影響には、主に以下の2つが挙げられます。
①配偶者控除が適用されなくなる
配偶者の年収が103万円超、または合計所得金額が48万円超の場合、配偶者控除は適用されず、所得税が増加する可能性があります。
➁配偶者特別控除に切り替わる可能性
配偶者の収入が制限額を超えても、条件を満たすと配偶者特別控除が適用され、控除額は収入に応じて段階的に減少します。
収入が制限額を超えた場合の対応策
一方で、収入が制限額を超えた場合の対応策として、以下3つの方法が挙げられます。
①年収の調整(働き方の見直し)
配偶者の年収が制限額を超えないよう、例えばパートタイムの勤務時間を減らして収入を103万円以下に抑えることで、配偶者控除を再適用できます。
➁配偶者特別控除を活用
配偶者の収入が制限額を超えた場合、配偶者特別控除が適用され、年収に応じて控除額が段階的に減少します。
③その他控除の活用
その他の活用可能な公的控除を利用することで、総所得を引き下げることが可能です。
FPに無料相談できるサイト
・【みらいのほけん】公式
まとめ
今回の記事のまとめです。
配偶者控除は、配偶者の所得が一定額以下の場合に納税者の税負担を軽減する制度です。
控除を受けるためには、配偶者が民法上の配偶者であり、納税者と生計を一にしていることなどの条件を満たす必要があります。
具体的には、配偶者の年収が103万円以下、または年間合計所得が48万円以下であることが求められますが、
配偶者特別控除やその他の控除を活用することで、再適用の可能性があります。
※この記事は令和6年11月時点で執筆したものです。控除額は今後変更される可能性がございますので、最新の情報については国税庁の公式サイトをご確認くださいますようお願い申し上げます。