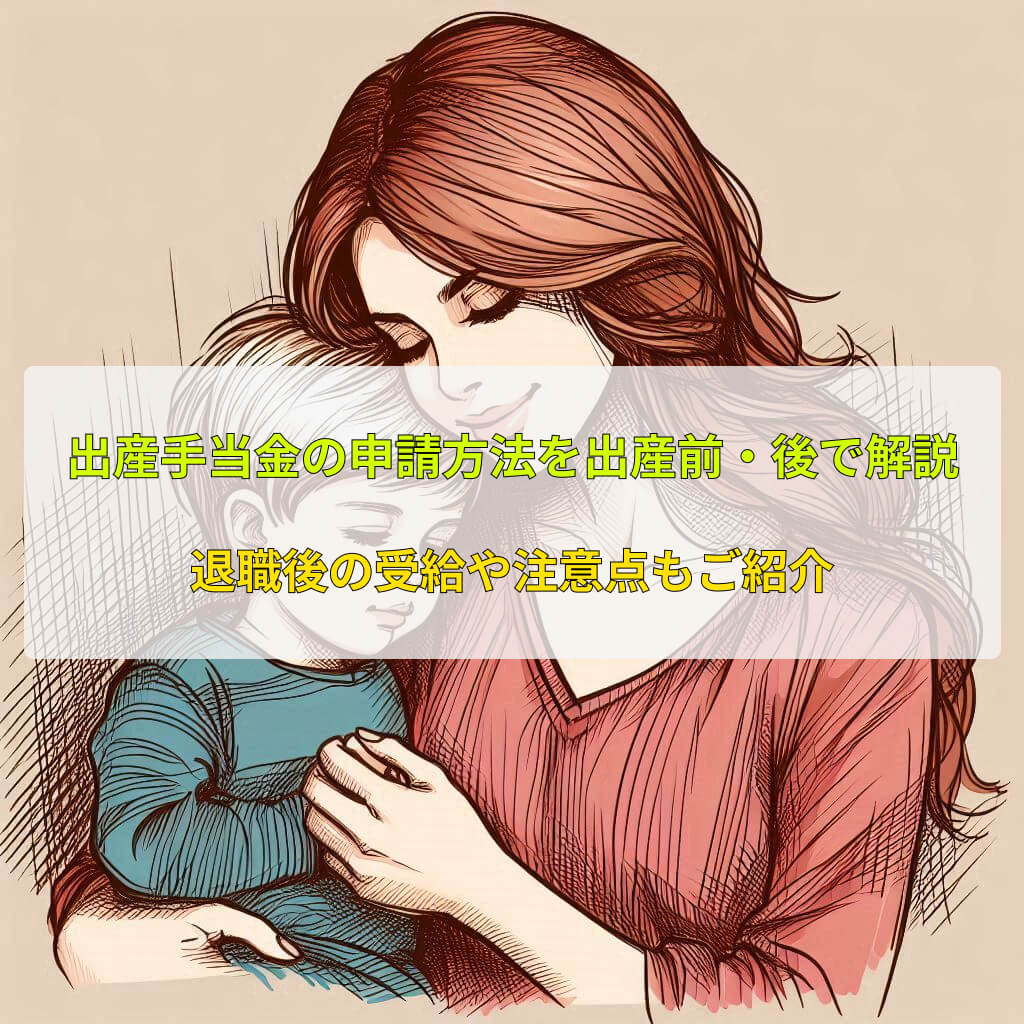近年、家庭内での役割分担が見直され、父親の育児参加が重要視されています。
そんな中、父親が子どもの出生に際して取得できる育児休業制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」が注目されています。
この制度を活用することで、父親は育児に積極的に関与し、母親をより献身的にサポートできるようになります。
今回の記事では、産後パパ育休の具体的な制度内容と、その取得方法について詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- 出生時育児休業の概要
- 出生時育児休業を活用することのメリット
- 育休取得前に準備しておくべきこととは?

育児・出産時に活用できる公的制度について学んでいきましょう。
出生時育児休業(産後パパ育休)の概要
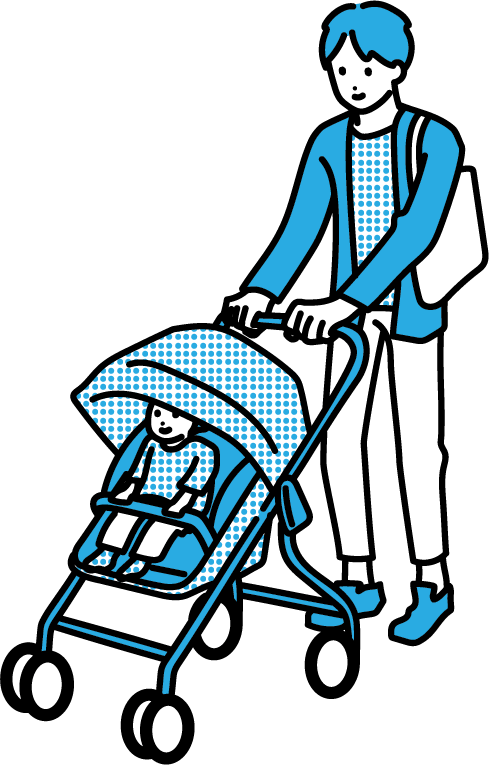
それでは最初に、出生時育児休業(産後パパ育休)の概要について見ていきましょう。
令和4年10月に導入されたこの制度ですが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

この制度の受給期間や受給金額について、詳しく見ていきましょう。
出生時育児休業の基礎知識
出生時育児休業(産後パパ育休)は、父親が子どもが生まれた際に取得できる育児休業制度です。
この制度では、子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間(28日間)の休暇を取得でき、従業員は希望する期間を選んで2回に分けて取得することも可能です。
出典:産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
受給期間
先ほどもお伝えしましたが、出生時育児休業(産後パパ育休)は、子どもが生まれた日から8週間以内に取得できる制度です。
そして具体的な条件は、主に以下の2つです。
①最長で4週間(28日間)の休暇が取得可能
➁休業期間は、希望する日数を選んで取得でき、2回に分割して取得することも可能
たとえば、赤ちゃんが生まれた日が4月1日だとします。
この場合、父親は4月1日から6月1日までの間に、最大28日間の育休を取得できます。
したがって、取得方法には以下の2つが考えられます。
Ⓐ一度に28日間取得
・4月1日から4月28日まで、一気に28日間の休暇を取得する方法。
Ⓑ2回に分割取得
・1回目:4月1日から4月14日までの14日間を取得。
・2回目:5月15日から5月28日までの14日間を取得。

ただし、申請は休業の2週間前までに行う必要があります。
受給金額
出生時育児休業を取得することで、育児休業給付金を受け取ることができます。
この給付金の金額は、取得開始から最初の6ヶ月間は給与の67%となりますが、給付金には上限が設定されています。
具体的には、2024年現在、育児休業給付金の上限は月額約30万円です。
例えば、休業開始時の賃金月額が30万円の場合、育児休業給付金は以下のように計算されます。
給付金額=休業開始時賃金日額(30万円 ÷ 30日 = 1万円) × 67% × 30日
= 20万1,000円
この場合、父親は育児休業中に月々20万1,000円の給付金を受け取ることができます。
しかし、給付金には上限があるため、月収が45万円を超える場合、給付金は上限の30万円が適用されます。
この点を踏まえて、給付金の金額は各自の状況によって異なることに注意が必要です。
出典:産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
出生時育児休業のメリット
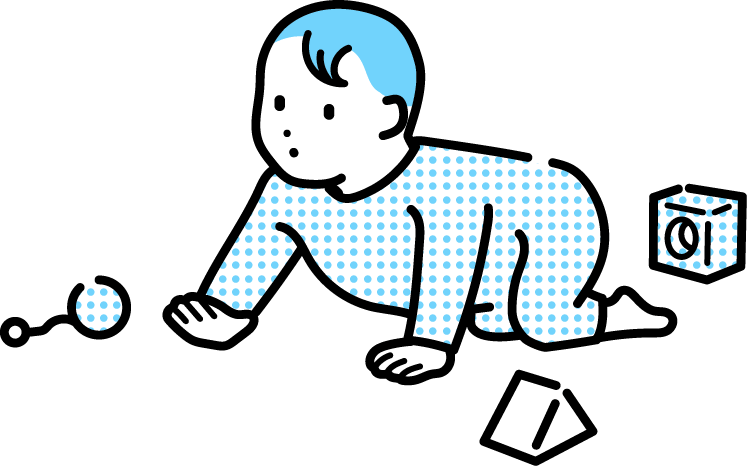
この制度を活用する目的の一つは経済的なサポートですが、その本質は公的制度を利用して育児に積極的に参加することにあります。

次に、出生時育児休業のメリットについて具体例を見ていきます。
育児負担の分担による母親のサポート
出生時育児休業のメリットの一つとして、育児負担の分担による母親のサポートが挙げられます。
育児中はストレスを抱え込みやすく、特に新生児期は体力的にも精神的にも疲れやすい時期です。
このような状況において、父親が育児に参加することで、母親の精神的な負担が軽減されます。
また、父親が育児に関与することで、自身の育児スキルも向上します。
この経験を通じて、父親は将来的に子育てに対する自信を持つことができ、家族全体にとってもプラスの影響を与えることが期待されます。
家計の見直しができるサイト
・【みらいのほけん】公式
産後パパ育休の取り方
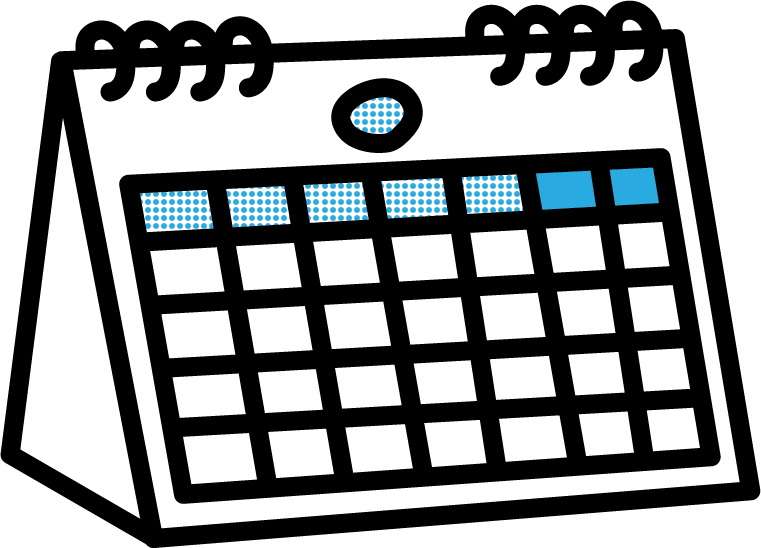
申請する際には、原則として休業開始の2週間前までに申請を行う必要があるなど、いくつか注意すべき点があります。

この章では、産後パパ育休の取得方法について確認しておきましょう。
休業の申請方法と注意点
出生時育児休業(産後パパ育休)を申請する際は、以下2つの要点を押さえておきましょう。
①休業開始予定日の確認と必要書類の準備
②会社を通じたハローワークへの申請
まず、会社の就業規則や育児休業に関する規定を確認し、必要な書類(出生証明書や育児休業申請書など)を準備します。
申請は、休業開始予定日の1ヶ月前には行うことが望ましく、これにより会社側ではスケジュール調整がしやすくなります。
また、育児休業給付金を受け取るためには、ハローワークへの申請が必要です。
この申請は、育児休業開始から8週間以内に、会社を通じて行うのが一般的です。
通常、育児休業中は就労が認められませんが、産後パパ育休の場合は、労使の合意があれば就労が可能です。
たとえば、育休中に「研修やセミナーに参加する」といった形で仕事を続けることができます。
育休取得前に確認しておきたいこととは?

育児休業中には、出生時育児休業以外にも活用できる公的制度がいくつかあります。

最後に、妊娠・出産時に活用できる公的制度についてご紹介します。
妊娠・出産に役立つ支援制度とその使い方
社会保険や助成金を活用することで、育児休業中の経済的支援や育児負担の軽減することができます。
そして、妊娠・出産に関連する社会保険や助成金には、以下3つのような制度があります。
1. 出産手当金
出産に伴う休業期間中、出産前42日(多胎妊娠は98日)と出産後56日間にわたり、給与の約67%が支給されます。
2. 育児休業給付金
育児休業を取得する際に支給される給付金で、育児休業開始から最初の6ヶ月間は給与の67%が支給され、以降は50%になります。
3. 健康保険の出産育児一時金
出産費用の負担軽減を目的とした一時金で、通常50万円支給されますが、出産する医療機関や状況によって支給額が異なる場合があります。(2025年1月時点)

より詳しい内容は、以下のコラム等をご参照ください。
参照コラム
・出産手当金っていつもらえるの?健康保険の気になるポイントを解説
・育児休業給付金の活用法|知っておきたい給付金を受け取るための条件とは?
まとめ
今回の記事のまとめです。
「産後パパ育休」は、父親が子どもの出生後に取得できる育児休業制度です。
近年、家庭内の役割分担が見直され、父親の育児参加がより重要視されています。
取得期間
・子どもの出生から8週間以内に、最長4週間(28日間)の休暇を取得可能。
取得方法
・希望する日数を選び、2回に分けて取得することも可能。
申請の注意点
・休業開始の2週間前までに申請が必要。
さらに、育休中は社会保険や助成金を活用することで、経済的な支援を受けながら、育児負担を軽減することができます。