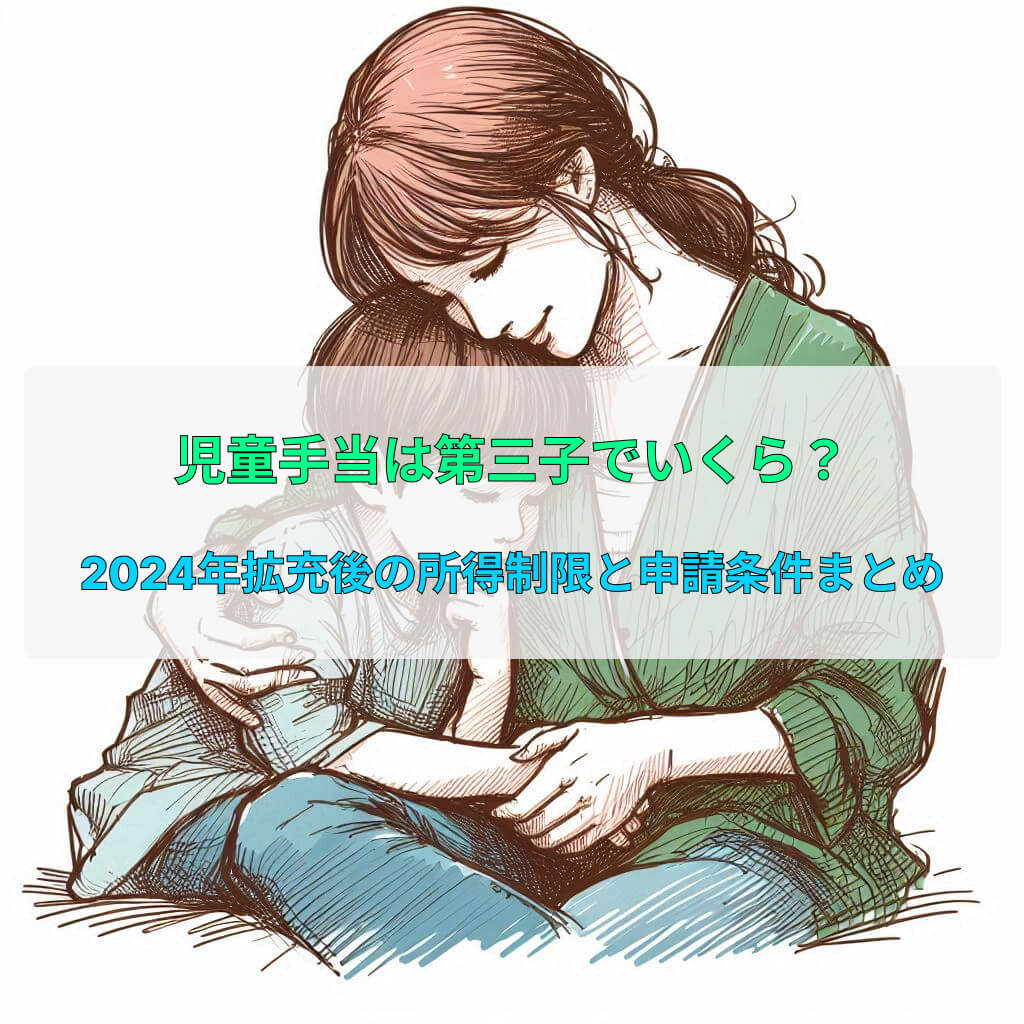『児童手当が拡充されたって本当?』
と聞かれると、意外と知らない方も多いかもしれません。
実は、2024年10月分から、児童手当の内容が拡充されました。
児童手当は、家庭の経済的負担を軽減するために国が支給する制度で、子どもの成長に合わせて支給される金額が決まっています。
この記事では、児童手当がいくら受け取れるのか、対象年齢やその条件について、わかりやすく解説していきます。
この記事で分かること
- 児童手当の概要
- 児童手当を受け取るための条件
- 児童手当の申請方法

支給期間が高校生年代まで延長されたことも、拡充内容の一つですよ!
あわせて読みたいコラム
・出産後の家計出費はどのくらい?子どもの将来に備える3つの家計管理ポイント
そもそも、児童手当とは?

冒頭でもお伝えした通り、2024年10月から児童手当の制度が拡充され、第3子以降の支給額が3万円に増額されるなどの変更があります。

まずはこの章で、児童手当の概要とその変更点を押さえていきましょう。
児童手当の概要
児童手当は、家庭の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長を支援するために国が支給する公的制度です。
そして、2024年10月からの改正により、児童手当の制度は以下のように拡充されました。
支給額
・0歳から3歳未満: 1万5千円
・3歳から小学校修了前: 月額1万円
・中学生: 月額1万円
・高校生: 月額1万円
・第3子以降: 月額3万円
対象者
・支給対象年齢: 0歳から高校生年代(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)
・対象世帯: 親等の経済的負担がある子どもを持つ世帯
支給時期
支払いは偶数月に年6回(2か月分ずつ)行われ、具体的には4月、6月、8月、10月、12月、2月に支給されます。
申請方法
児童手当を受けるには、住民票のある市区町村の窓口で申請し、申請書や本人確認書類、振込先口座情報などを準備する必要があります。
参照サイト
・政府広報オンライン『2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を』
第3子以降の定義について
先ほど述べた支給額の対象者に関して、特に「第3子以降」について整理してみたいと思います。
「第3子以降」という表現は、高校卒業までの子どもの中で3番目以降の子どもを指します。
具体的には、0歳から18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの子どもが対象となります。
たとえば、子どもが高校生1人と中学生2人の場合、支給額は以下のようになります。
中学生1人目: 月額1万円
中学生2人目(第3子): 月額3万円(多子世帯への支援)
高校生: 月額1万円
したがって、合計で月額5万円の支給となります。

第3子以降のカウント方法については、こども家庭庁の公式サイトをご参照ください。
参照サイト
・こども家庭庁『「第3子以降」のカウント方法について』
児童手当を受け取るための条件

ところで気になるのが、高所得者にも制限はないの?という点です。
2024年10月の制度改正により、主たる生計者の年収が960万円を超える世帯でも、所得に関係なく児童手当が全額支給されるようになりました。

この章では、児童手当を受け取る際の所得制限について確認していきます。
児童手当の所得制限とは?
児童手当を受け取るための条件の一つに、所得制限があります。
この所得制限は、家庭の収入に応じて支給額が異なるため、経済的状況に基づいて手当が支給される仕組みです。
例えば、主たる生計者の年収が960万円以上の場合、従来は所得制限に該当し、手当の支給が減額される可能性がありました。
しかし、同年の改正により、所得にかかわらず全額支給されることになりました。
児童扶養手当と併用はできるの?
児童扶養手当は、ひとり親家庭など、経済的な支援が必要な家庭を対象とした制度です。
子どもの年齢や世帯の所得に応じて支給額が決まり、第2子以降も対象になります。
そのため、児童手当を受け取りながら児童扶養手当も併用することで、子育てにかかる経済的負担をより軽くすることができます。
児童扶養手当の3つのポイント
①対象年齢
0歳から18歳の年度末まで(障害のある子どもは20歳未満)
②支給額
所得に応じて10,740円〜45,490円程度(第2子以降は5,380円〜10,750円)
③支給日
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)

児童扶養手当も令和6年に一部制度が拡充されているため、詳細は公式サイトでご確認ください。
参照サイト
・こども家庭庁『児童扶養手当について』
児童手当の申請方法
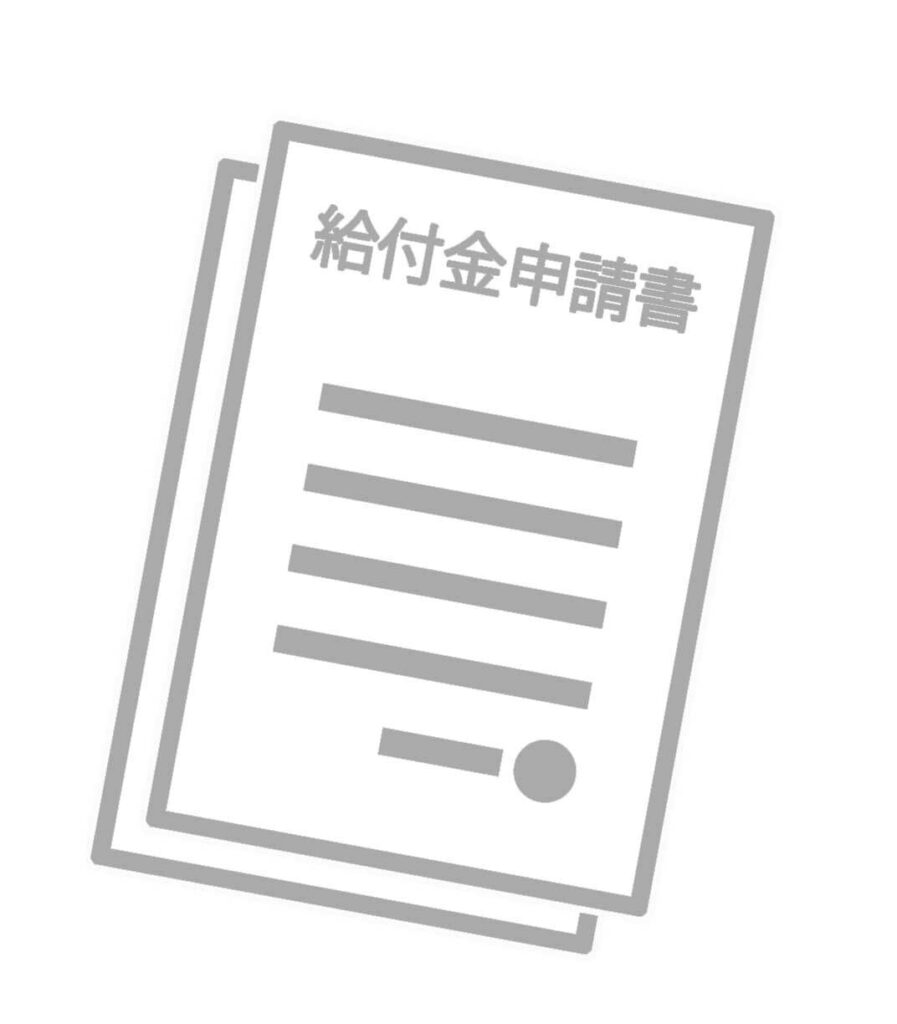
子どもが生まれて初めて児童手当を受け取るには、出産後に「認定請求」の手続きが必要です。
この申請を行うことで、児童手当の受給資格が認定され、手当が支給されます。

最後に、児童手当の具体的な申請方法について見ていきましょう。
申請に必要な書類
児童手当の申請には、主に以下の5つの書類が必要です。
①健康保険証のコピー
健康保険の証明書には、氏名、保険者番号、加入者番号などが記載されており、申請者の健康保険加入状況を確認するために必要です。
➁申請者名義の口座が確認できるもの
振込先の口座情報が確認できる通帳やキャッシュカードのコピーが必要です。
③申請者および配偶者のマイナンバーが確認できる書類のコピー
個人番号カードや個人番号通知カードなど、申請者および配偶者のマイナンバーが確認できる書類のコピーが必要です。
④申請者の印鑑
実印や認印など、申請書に押印するために必要です。
⑤申請者本人確認書類
本人確認のため、運転免許証、パスポート、個人番号カード、健康保険証、年金手帳、または住民票の写しのいずれかが必要です。
公的制度に関するコラム
・出生時育児休業の取得方法とは?産後パパ育休前に準備しておくべきこと
申請方法(認定請求申請を含む手続きの流れ)
申請時には以下3つのポイントをおさえておきましょう。
①申請期限
出生翌日から15日以内に申請が必要で、期限を過ぎるとその月分の児童手当が受け取れない可能性があります。
➁申請先
居住する市区町村窓口で申請を行います(公務員は勤務先から支給されます)。
③必要書類の提出
申請に必要な書類等を申請先に提出します。

ただし、公務員の場合は申請方法などが異なるため、必ずこども家庭庁の公式サイトで詳細をご確認ください。
参照サイト
・児童手当制度の概要|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
まとめ
今回の記事のまとめです。
児童手当は、家庭の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長を支援するための制度です。
対象は、0歳から高校生(18歳の誕生日後、最初の3月末まで)の子どもがいる家庭で、支給は年6回、偶数月に2か月分ずつ行われます。
手当を受けるには、市区町村の窓口で申請が必要で、以下の書類等を準備しましょう。
・請求者の健康保険証のコピー
・請求者名義の口座情報
・請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
・印鑑
・本人確認書類