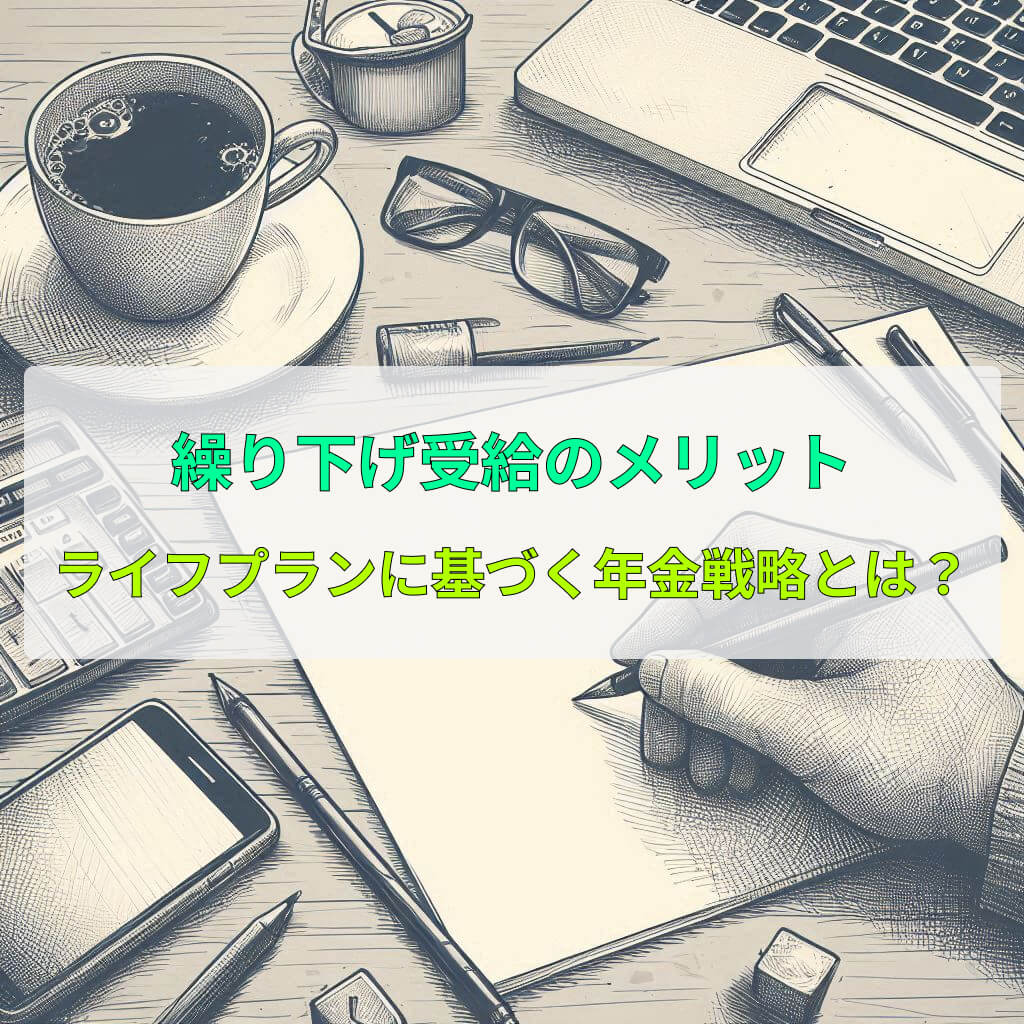『年金の繰り下げ受給のメリットって?』
年金の繰り下げ受給を選択すると、受け取る年金額が増えるという大きなメリットがあります。
具体的には、年金を受け取る開始年齢を最大で5年間遅らせることで、受給額が1ヶ月ごとに0.7%増加し、最大で84%まで増額されます。
これにより、老後の長期間にわたって安定した収入源を確保できる点が大きな魅力です。
今回の記事では、繰り下げ受給の具体的なメリットを解説し、どのような状況で繰り下げ受給を選択するべきかについて考察していきます。
この記事で分かること
- 繰り下げ受給の概要
- 繰り下げ受給を選択するメリット
- 繰り下げ受給のシミュレーション
繰り下げ受給の仕組み
年金の繰り下げ受給とは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始時期を遅らせることですが、実は基礎年金だけを遅らせることができることをご存知でしょうか。
まずは、この繰り下げ受給の仕組みについて詳しく見ていきましょう。

公的年金の基本的な概要から確認していきましょう!
老齢基礎年金と厚生年金の関係
老齢基礎年金と厚生年金は、日本の公的年金制度の2本の柱であり、主に老後の生活資金を支えるために設計されています。
基礎年金は、すべての人が受け取ることができる最低限の年金であり、厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。

2つの特徴をまとめると、以下の図1のようになります。
| 項目 | 老齢基礎年金 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象者 | 自営業者、フリーランス、専業主婦、会社員など、全国民が対象 | 会社員、公務員などの給与所得者が対象 |
| 受給条件 | 20歳から60歳までに国民年金保険料を納めること | 企業や公的機関が保険料を従業員と折半して支払う |
| 受給開始年齢 | 原則65歳(繰り上げ受給・繰り下げ受給が可能) | 原則65歳(基礎年金に上乗せして支給される) |
| 受給額 | 一定額(2024年時点で満額約6万8,000円) | 働いた期間や給与額に応じて報酬比例で変動する |
老齢基礎年金と厚生年金、別々に繰り下げ受給ができる
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、65歳で受け取るのではなく、66歳から75歳の間に繰り下げて受給することが可能です。
この繰り下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金それぞれについて別々に選択でき、繰り下げることで年金額が増加します。
増額された年金額は受給期間中に変動せず、増額率は最大で、84%に達することがあります。
増額率(最大84%) = 0.7% × (65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数)

※繰り上げ受給は、2つを同時に受給することはできないので、注意が必要です。
参照サイト
・日本年金機構『年金の繰上げ受給』
繰り下げ受給を選択するメリットとは?
では次に、繰り下げ受給を選択するメリットについて見ていきましょう。
年金は原則65歳から受給できますが、65歳以降に繰り下げて受給することには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

当たり前ですが、受給額が増えることで、老後のライフプランが計画的に進めやすくなりますね。
3つのメリット
繰り下げ受給の主なメリットには、以下の3つが挙げられます。
①年金額の増加
65歳ではなく66歳以降に受け取ることで、受給額が増額され、最大で84%増加する可能性があります。
➁長寿リスクへの備え
受給額の増加は、老後の生活費の安定に繋がり、長寿社会に対する備えにもなります。
③税金面でのメリット
受給開始を遅らせることで、受け取る期間までの総所得を抑え、税負担を軽減できる場合があります。

特に、現在では『老後2000万円問題』とも言われていますよね。
合わせて読みたいコラム
・老後資産2,000万円、どのように準備する?
受給額増加のシュミレーション
先ほど、繰り下げ受給のメリットとして受給額の増加を挙げました。
年金を繰り下げて受給する最大のメリットは、この受給額の増加にあります。
ここでは、その具体的な算出方法について見ていきます。
ポイントとなるのは、繰り下げた月数に応じて受給額が増加するという点です。
具体的には、繰り下げた月数に0.7%を掛けた増加分が適用されます。
たとえば、一年間繰り下げる場合の計算は以下の通りです。
0.7% × 12か月 = 8.4%
このように、繰り下げることで受給額が1年で8.4%増加します。
以上を踏まえて、繰り下げ増額率の早見表を以下図2にまとめてみます。

以下の表で、年齢別の手取り額の変化を確認してみてくださいね!
| 請求時の年齢(繰り下げた月数) | 増額率 |
|---|---|
| 66歳(12か月) | 8.4% |
| 67歳(24か月) | 16.8% |
| 68歳(36か月) | 25.2% |
| 69歳(48か月) | 33.6% |
| 70歳(60か月) | 42.0% |
| 71歳(72か月) | 50.4% |
| 72歳(84か月) | 58.8% |
| 73歳(96か月) | 67.2% |
| 74歳(108か月) | 75.6% |
| 75歳(120か月) | 84.0% |
出典:日本年金機構『年金の繰り下げ受給』
繰り下げ受給を選択したほうがいいケースとは?
これまでお伝えしたように、繰り下げ受給には多くのメリットがありますが、選択時にはいくつかの注意点もあります。
最後に、繰り下げ受給を選ぶべきケースについて考えてみましょう。
ライフプランに基づく受給戦略
繰り下げ受給を選択することが望ましいケースには、大きく分けて以下の3点が考えられます。
①年金受給を急がない場合
年金をすぐに受け取る必要がなく、別の収入源があり退職後も働く意欲がある方には、繰り下げ受給が適しています。
➁経済的に余裕がある場合
現在の生活費が他の収入で賄える状況であれば、繰り下げ受給を選ぶことで将来的な年金額を増加させ、経済的な安定を図ることができます。
③年金の税負担を考慮する場合
年金受給開始時の税負担を軽減したい方は、繰り下げ受給を選択することで受給開始時期を遅らせ、結果的に受け取る年金額を増やすことが可能です。

つまり、経済的に余裕があり、年金受給を急がない場合や、税負担を軽減したい方に適していると言えます。
年金について相談したい場合は?
年金について相談したい場合には、年金事務所に問い合わせるだけでなく、ファイナンシャルプランナー(FP)を活用するのも一つの手段です。
FPにシュミレーションを行ってもらう
ファイナンシャルプランナー(FP)に、年金受給のシミュレーションをしてもらいましょう。
FPは、個々のライフプランや財政状況に基づいて、最適な年金受給プランを提案します。
また、FPは年金受給にとどまらず、保険や資産運用などお金全般に関する豊富な知識を持っているため、トータル的なライフプランのアドバイスを受けることができます。
これにより、将来的な経済状況やライフイベントに基づくリスクを評価し、年金をどのように活用するかについて具体的なアドバイスを得ることができます。

以下のコラムでは、FPの役割についてまとめているので、合わせてご参照ください。
参照コラム
・AFPとはどんな資格?AFP合格者にしかできないこと
まとめ
今回の記事のまとめです。
繰り下げ受給には多くのメリットがありますが、最大の利点は年金額が増えることです。
受給開始を遅らせることで、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が増額され、将来の生活安定に繋がります。
繰り下げ受給は、66歳から75歳の間で選択可能で、老齢基礎年金と老齢厚生年金をそれぞれ別々に選べる点が特徴です。
年金の受給タイミングや額について詳細に相談したい場合は、FPにシミュレーションを依頼するのが効果的です。