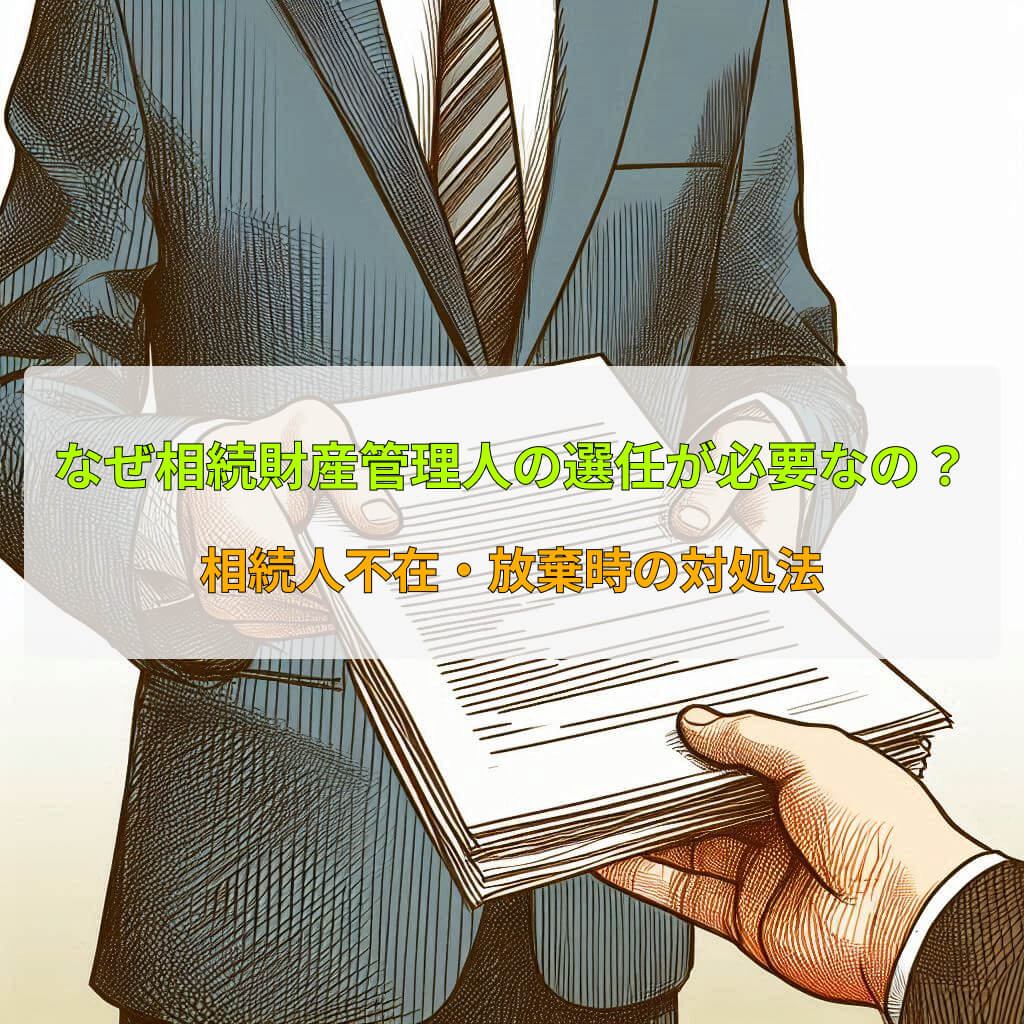『相続財産管理人って、どんな時に必要なの?』
日常生活では、「相続財産管理人」という言葉はあまり馴染みがないかもしれません。
しかし、相続財産管理人は、相続手続きを円滑に進めるために欠かせない存在です。
具体的には、相続財産の管理や、場合によっては財産を国庫に帰属させる役割を担う人を指します。
本記事では、相続財産管理人の役割や選任方法について詳しく解説し、相続手続きをスムーズに進めるためのポイントについて見ていきましょう。
この記事でわかること
- 相続財産管理人の概要
- 相続財産管理人の選任がなぜ必要なのか
- 相続財産管理人を選ぶ際の注意点

相続財産管理人が行えることについて見ていきましょう。
そもそも、相続財産管理人とは?
冒頭でもお伝えした通り、日常生活ではあまり聞きなじみのない言葉なので、相続財産管理人がなぜ必要なのかが分かりにくいかもしれません。
まずは、相続財産管理人の役割について見ていきましょう。
相続財産管理人の定義と役割
相続財産管理人とは、相続人が不明であったり、相続人全員が相続放棄をした場合など、通常の相続手続きが進まない状況において、相続財産の管理や処分を行う役割を担う人物を指します。
(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
出典:民法|e-Gov法令検索
相続財産管理人が必要なケースとは?
相続財産管理人が選任される状況として、以下の2つのケースが該当します。
①相続人が不在または不明の場合
相続人が不在または不明な場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、財産の管理を行います。
②相続人全員が相続放棄をした場合
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人が選任され、財産の管理や処分が行われます。

また、遺贈に伴い第三者に遺産を引き継ぐ場合にも、相続財産管理人が選任される可能性があります。
遺贈に関するコラム
・遺贈で譲渡できる財産とは?仕組みと注意点を解説
相続財産管理人の選任方法と要件
相続財産管理人の主な役割には、以下4つが挙げられます。
①相続財産の管理
相続財産管理人は、相続財産を適切に管理し、リストアップして保護する役割を果たします。
②相続債務の整理
相続財産管理人は、被相続人の残した債務を整理し、必要な返済手続きを行います。
③相続財産の処分
相続財産管理人は、相続財産を処分し、場合によっては国庫に帰属させる手続きを行います。
④相続手続きの代行
相続財産管理人は、相続税申告や登記手続き、保険金請求などの相続手続きを代行します。

上記4つについては、次の章で詳しく見ていきます。
なぜ相続財産管理人の選任が必要なのか
相続財産管理人の選任が必要な理由には、以下の4つがあげられます。
①相続財産の適切な保護と管理
相続財産管理人は、財産の劣化や価値の減少を防ぎ、適切に保護・管理する役割を担います。
②遺産分割の遅延を防ぐため
相続財産管理人は、相続人がいない場合でも相続手続きを円滑に進め、遺産分割の遅延を防ぎます。
③債権者が返済を求めている場合の対応
相続財産管理人は、相続財産を管理し、債務返済が適切に行われるよう調整します。
④相続放棄した人が管理責任を免れるため
相続放棄をした人は、相続財産の管理に関する責任から解放されますが、その義務を免れるために相続財産管理人が選任され、管理・清算が行われます。

相続放棄後も、相続財産が適切に管理されるまでは、自身の財産と同様に管理する義務があります。
出典:
法務省『財産管理制度の見直し(相続を放棄した者の義務)』

相続財産管理人の仕事の詳細
相続財産管理人が行える業務には、預貯金口座の解約や払戻し、不動産登記申請などが含まれます。
次に、この章では、相続財産管理人が具体的にどのような業務を行えるのか、詳細に見ていきましょう。
相続財産管理人が行えること
相続財産管理人の主な業務は、保存行為および管理行為と処分行為に分けられます。
Ⓐ保存・管理行為(許可不要)
相続財産の現状維持や利用・改良を行う業務で、以下のような行為などが含まれます。
・不動産の相続登記
・預金の払い戻し
・預金口座の解約
・賃貸借契約の解除
・債務の弁済
Ⓑ処分行為(家庭裁判所の許可が必要)
財産の価値や状態を変える行為で、家庭裁判所の許可を得て行います。
・不動産の売却
・家具や家電の処分
・墓地購入や永代供養費
相続財産清算人の選任を申請できる人
相続財産清算人の選任を申請できる人について、以下の2つの関係者が挙げられます。
Ⓐ相続財産に関連する利害関係者
相続財産に関連する利害関係者とは、相続財産の管理や清算に直接的な関係がある人物や団体を指します。
具体的には、相続人や債権者、特別縁故者など、相続に関わる利害関係者が該当します。
これらの利害関係者は、自身の利益を守るため、相続財産の適切な管理や清算を確保する目的で、相続財産清算人の選任を申請することができます。

特別縁故者とは、被相続人と生計を共にした人(内縁の妻・夫など)や療養看護に努めた人など、裁判所が認めた特別な関係者を指します。
Ⓑ検察官
検察官も相続財産清算人の選任を申請することができます。
これは、相続財産の管理に関して公共の利益が関わる場合、特に相続人が不明または不在であったり、相続財産の処理に関して疑義が生じた場合などに、検察官がその選任を申し立てることができるというものです。
管理義務の対象となる遺産
相続放棄をしても、空き家、空き地、農地、山林などの財産には管理義務が生じることがあります。
これらの財産は相続財産として残るため、相続財産管理人がその管理を担当することになります。
例えば、空き家は放置しておくと損壊や不法侵入のリスクが高まるため、適切に維持・管理する必要があります。
空き地も放置すると固定資産税が発生するため、管理が欠かせません。
また、農地は耕作の有無にかかわらず、農地として管理しなければならず、山林に関しては森林法に基づいた管理が必要です。

土地国庫帰属制度は、特定の条件のもとで土地を国に返還する制度で、土地の所有者が一定の理由により土地を国に返還することができます。
参照コラム
・相続土地国庫帰属制度を活用するための条件とは?
相続手続きで気を付けるべきポイント
相続財産清算人が選任される要件には、戸籍上の相続人が見当たらない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合などが挙げられます。
最後に、相続手続きで注意すべきポイントについて見ていきましょう。
相続財産管理人を選ぶ際の注意点
相続財産管理人を選任する際の注意点として、以下の6つのポイントが挙げられます。
1. 信頼できる人物を選ぶ
相続財産管理人は、相続財産の適切な管理や債務の弁済、相続手続きの遂行を任される役割を担います。
そのため、相続人との関係や財産管理に関する知識・経験を考慮し、信頼できる身近な人物を選ぶことが大切です。
2. 相続人との調整能力
相続財産管理人は、相続人間での意見の違いや対立を調整する役割も果たします。
したがって、コミュニケーション能力が高く、公平に物事を進められる人物を選ぶことが望ましいです。
3. 財産の内容に精通していること
相続財産には不動産や金融資産、借金などさまざまな種類があります。
そのため、選ばれた管理人が財産管理に必要な知識を持っていることも大切です。
4. 相続財産管理人の報酬について確認
相続財産管理人には報酬が発生する場合があります。
報酬の金額が不明確だったり、高額すぎると後々トラブルの原因となる可能性があるため、報酬額や支払い条件についてはあらかじめ相続人と合意しておくことが大切です。
5. 法的要件を満たすこと
相続財産管理人を選ぶ際には、法的な要件や手続きに従う必要があります。
例えば、相続人に未成年者や成年後見人がいる場合など、法的要件を満たしていないと、その選任が無効になる可能性があります。
6. 専門家への依頼を検討
相続財産管理人としての責任を果たすには、専門的な知識や経験が求められます。
特に、遺産に複雑な事情がある場合(企業の株式や海外の資産など)は、弁護士や税理士などの専門家に依頼することを検討した方が適切な場合があります。

当サイトの他のコラムでは、専門家活用のメリットについても触れていますので、ぜひご参考にしてください。
参照コラム
・遺産分割協議書の作成費用は?4つの専門家ごとに比較!
まとめ
今回の記事のまとめです。
相続財産管理人は、相続人が不在、または相続人全員が相続放棄した場合に、家庭裁判所によって選任されます。
主な役割としては、相続財産の管理、債務の整理、財産の処分、そして相続手続きの代行が挙げられます。
これらの業務は、保存・管理行為と処分行為に分類され、相続財産清算人の選任申請は、利害関係者や検察官が行うことができます。