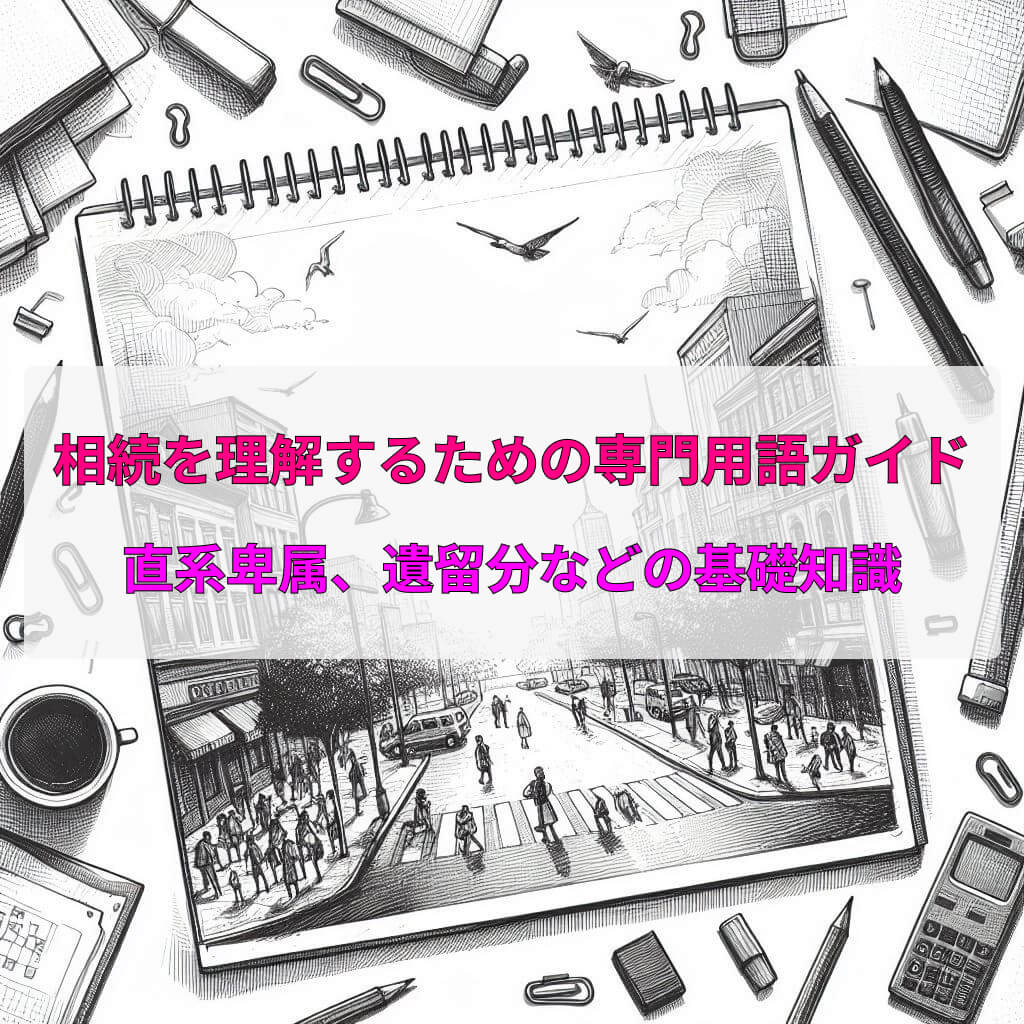相続は私たちの身近な出来事ですが、実際にその場に立ち会うと、普段耳にしない専門用語が数多く登場しますよね。
特に「遺留分」や「直系卑属」など、普段使い慣れない言葉が多いため、戸惑う方も多いかもしれません。
この記事では、相続に関連する専門用語をわかりやすく解説し、相続の流れや注意点についても解説していきます。
この記事でわかること
- 相続における専門用語の基礎知識
- 相続に関する専門用語8つ
- 相続時に活用できる専門家

相続に関する専門用語について、一緒に学んでいきましょう。
相続における専門用語の基礎知識
相続は、遺産分割や相続税の申告など、予想以上に多くの手続きや調整が必要です。
特に、親族間で意見が分かれることもあるため、精神的・物理的に大きな負担となることが少なくありません。
こうした負担を軽減するためにも、相続に関する基本的な知識をしっかりと把握しておくことが重要です。
相続は専門用語が多い
相続は、法律的かつ税務的な側面が強いため、多くの専門用語が登場します。
これらの用語は、日常生活ではあまり使われないことが多く、特に初めて相続に関わる場合や、相続手続きに慣れていない方にとっては理解しにくい部分もあります。

専門用語が多いため、相続手続きが複雑に感じられ、どこから手をつけてよいのか分からなくなることもあります。
相続における専門用語が難しい理由
相続における専門用語が難しい理由の一つは、用語が状況によって異なる意味を持つことです。
例えば、「相続人」という言葉も、遺言がある場合とない場合で意味が変わります。
さらに、相続税の計算には細かい用語が必要で、正しく理解して適用することが求められます。
また、相続は法律、税務、登記、金融機関など複数の分野に関わり、それぞれに専門用語があります。

専門家を活用する最大のメリットは、専門知識に基づいた適切なサポートを受けられることです。
法律用語と税務用語の違い
相続に関わる専門用語は、大きく分けて「法律用語」と「税務用語」の2つに分類されます。
法律用語
相続人や遺言、遺産分割などは、誰がどのように相続するかを決めるための言葉です。
これらの用語は、法的な権利や義務を明確にするために使用されます。
例えば、「法定相続人」や「遺産分割協議」などは、相続に関する決定を行う際に必要となります。
税務用語
相続税の計算や納付に関わる用語は、遺産の評価額や相続税の課税基準など、税務的な側面を理解するために必要です。
例えば、「基礎控除」や「課税遺産総額」といった用語は、相続税を計算する際に理解しておくべき基本的な概念の一つです。

次の章では、その専門用語について詳しく見ていきましょう。
相続について相談できるサイト
・相続税に特化したFP無料相談
相続に関する専門用語8つ
次に、この章では、相続に関する専門用語について見ていきましょう。
前章で説明したように、相続には法律用語と税務用語がありますが、
今回は、その中でも、特に耳にする機会が多い8つの用語をそれぞれピックアップし、それぞれの意味と役割についてご紹介します。
相続に関する8つの法律用語
1. 遺言執行者
遺言書に基づき、遺産の分割や相続手続きなどを実行する責任を負う人物。遺言執行者は遺言者が指定することができます。
2. 直系卑属
親から子、孫へと続く直接の血縁関係にある人々。例えば、子供や孫が該当します。
3. 直系尊属
血縁関係がある人々のうち、本人より前の世代にあたる人々。例えば、親や祖父母が該当します。
4. 遺留分
相続人が最低限受け取る権利が保障された相続分。遺言によって不公平に扱われないよう、一定の割合で遺産を請求できます。
5. 相続開始
被相続人の死亡により、相続が開始されること。相続開始時に相続人が決定し、相続手続きが始まります。
6. 遺産分割協議
相続人が集まり、遺産をどのように分けるかを話し合う手続き。合意に達すると「遺産分割協議書」が作成されます。
7. 特別受益
相続人が生前に贈与を受けた場合、その贈与額を相続分に反映させるための制度。特別受益者は相続分が減額されることがあります。
8. 遺贈
遺言により、法定相続人以外の人物に財産を贈ること。遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。
合わせて読みたいコラム
・遺産分割協議書の作成費用は?4つの専門家ごとに比較!
相続に関する8つの税務用語
1. 相続時精算課税制度
生前に贈与を受けた財産を相続時に合算して相続税を計算する制度。
2. 小規模宅地等の特例
自宅などの不動産について、特定の条件を満たす場合に相続税が軽減される特例。
3. 物納
相続税を現金ではなく、土地や建物などの「物」で納める方法。
4. 延納
相続税を一括で納めるのではなく、分割して納める方法。
5. 相続税の納税猶予
相続税の納付を延期することができる制度。特に農地や事業用財産に適用される。
6. 遺産の分割方法(分割比率)
相続人間で財産をどのように分けるかを決定する割合。
7. 財産評価基準
相続税の計算において、相続財産の評価基準を定めた基準。
8. みなし贈与
相続税の計算時に、一定の贈与が相続財産としてみなされること。
合わせて読みたいコラム
・相続時精算課税制度ってどんな制度?概要や仕組みについての解説
相続については誰に相談すればいいの?
繰り返しになりますが、相続は法律、税務、登記、金融機関など、複数の分野に関わるため、ひとりで解決しようとすると大きな負担がかかることがあります。
では、最後に、相続時の相談先について見ていきましょう。
相続に関して相談できる6つの相談先
相続に関する相談をする際には、以下6つの専門家に相談するのが一般的です。

ただし、それぞれの専門家が異なる役割を持っているので、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが大切ですよ!
1. 弁護士
役割
相続に関する法律問題(遺産分割や遺言書の有効性、相続人間のトラブルなど)に法的アドバイスや調停を行います。
相談のタイミング
相続人間でトラブルが発生した場合や、遺言書の内容が不明確で争いになりそうな場合など、法的な判断が必要な場合。
2. 税理士
役割
相続税の申告・計算や節税対策のアドバイスを行い、税負担の軽減方法をサポートします。
相談のタイミング
相続税が発生する場合や、遺産の評価額が不明な場合、節税対策を講じたい場合。
3. 司法書士
役割
不動産の相続登記手続きをサポートし、名義変更に必要な書類を整備して登記を代行します。
相談のタイミング
不動産の相続登記をする必要がある場合。
4. 信託銀行や金融機関
役割
亡くなった方の金融資産の手続きや、遺言信託・資産管理サービスに関するアドバイスを提供します。
相談のタイミング
亡くなった方の金融資産(預金口座、証券など)の手続きが必要な場合。
5. 行政書士
役割
相続手続きに必要な書類の作成をサポートします。
相談のタイミング
相続の手続きに関する書類作成やアドバイスが必要な場合。
6. ファイナンシャルプランナー(FP)
役割
資産運用や生活設計に関する総括的なサポートを行います。
相談のタイミング
相続における財産の分け方や生活設計を考える場合。

相続に関して、相談先や相談機関については以下のコラムでも解説しているので、あわせてご参照ください。
参照コラム
・遺産分割協議書の作成費用は?4つの専門家ごとに比較!
まとめ
今回の記事のまとめです。
相続における専門用語が難しい理由の一つは、用語が状況によって異なる意味を持つことです。
相続に関わる用語は大きく「法律用語」と「税務用語」の2つに分類され、これらを適切に理解することで相続時の精神的・物理的な負担を軽減できます。