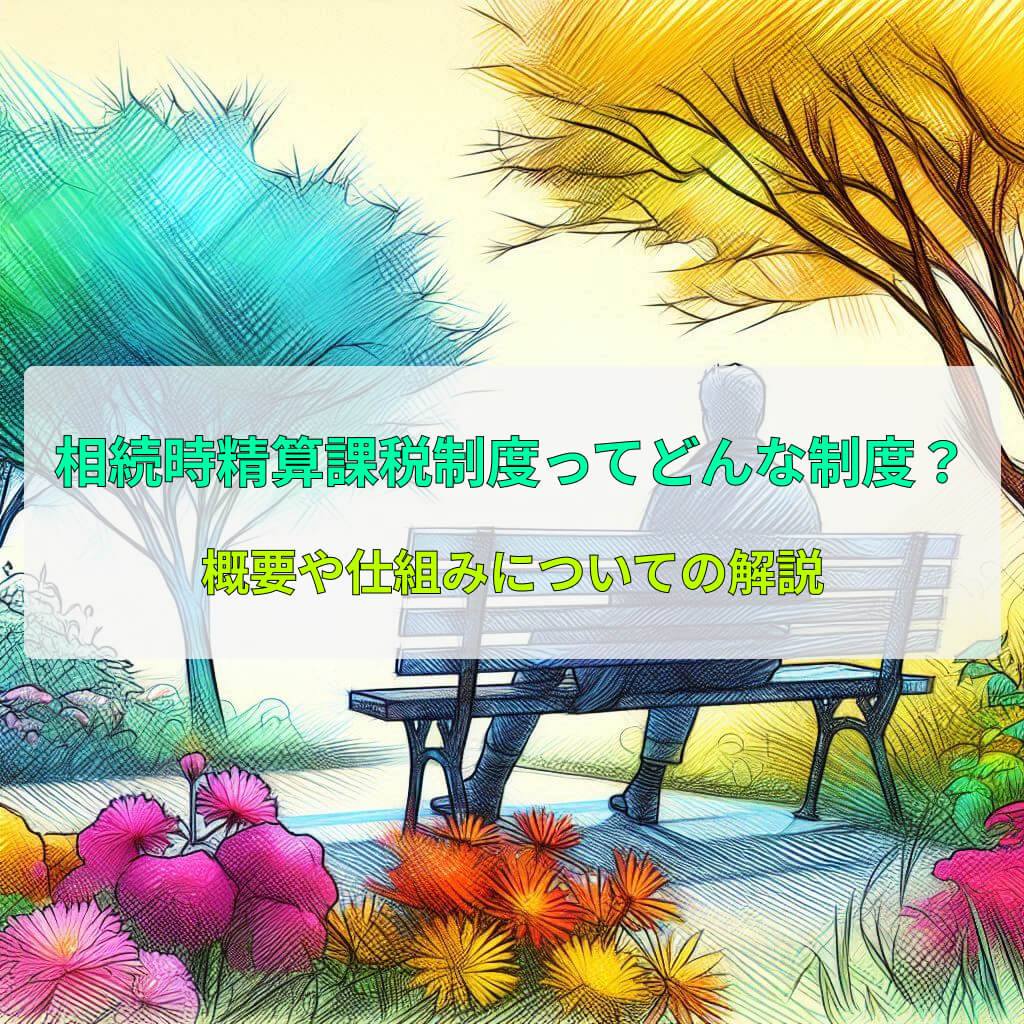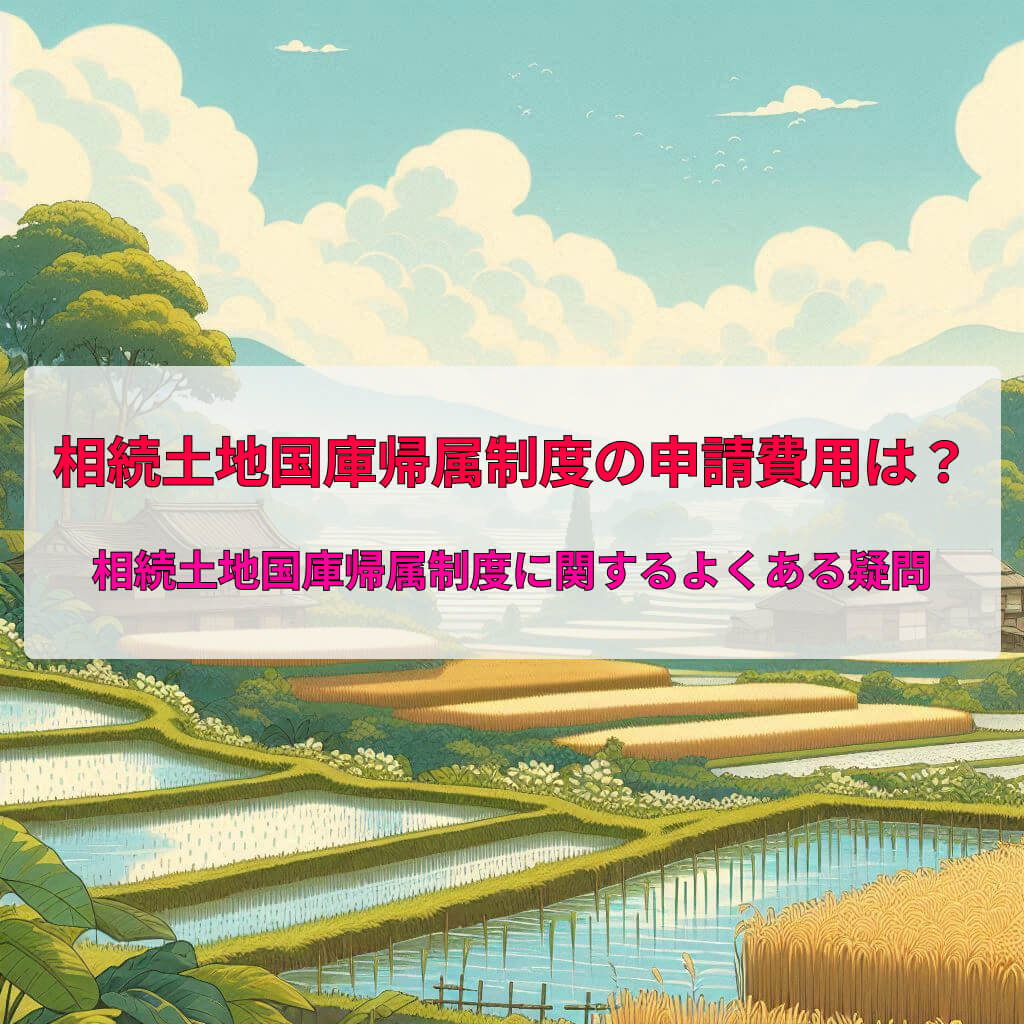相続放棄は、相続人が故人の遺産を受け取らないことを決定する手続きです。
相続が開始されると、相続人はその財産や負債を引き継ぐことになりますが、借金や過剰な負担を避けるために相続放棄を選択することができます。
しかし相続放棄には、手続き方法や申告期限など厳格なルールが定められているため、事前に正しい知識を身につけておくことが大切です。
この記事では、相続放棄の基本的な概要と、実際に活用するまでの流れについて学んでいきましょう。
この記事でわかること
- 相続放棄の基本的な概要
- 相続放棄を活用することのメリットとデメリット
- 相続放棄の手続き方法

相続トラブルは身近な問題だからこそ、正しい知識を身につけておきましょう。
そもそも、相続放棄とは?
相続放棄とは、その名の通り、故人の財産を受け継がないことを決定する手続きです。
この手続きを行うことで、遺産の中に含まれる財産だけでなく、負債も引き継がずに済むため、相続人の過剰な負担を避けることができます。
まずは、相続放棄の基本的な概要を見ていきましょう。

ちなみに、相続放棄せずに借金を放置すると、相続人の財産が差し押さえられる可能性があります。
相続放棄の基本的な概要
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産や負債を一切受け継がないことを選択する手続きです。
これにより、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払いの税金など)も相続しなくなります。
相続放棄の主な特徴は、以下の4点です。
①相続権の放棄
相続放棄を行うと、相続権そのものを放棄し、遺産(財産および負債)を一切引き継がず、最初から相続人でない扱いとなります。
②負債の免除
相続放棄を選ぶことで、故人の負債を引き継ぐことなく、負債の支払い義務から解放されます。
③家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄は家庭裁判所に申立てを行い、手続きを経て正式に放棄が認められ、申立ては相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
④放棄後の遺産の取り決めは他の相続人に委ねられる
相続放棄をした場合、その相続分は他の相続人に分配され、放棄した人はその後の遺産分割に関与しません。
相続放棄の主な理由
相続放棄を選択する理由として、主に以下の3つが考えられます。
①多額の負債がある場合
借金や未払いの税金など、負債が多い場合に相続放棄をすることで、経済的なリスクを回避できます。
②相続争いを避けるため
相続人同士の争いを避けるため、相続放棄を選ぶことでトラブルを回避できます。
③特定の相続人に譲るため
特定の相続人に財産を集約したい場合、他の相続人が相続放棄をすることで、遺産をスムーズに移転できます。

上記の理由や主なメリットについては、第2章で詳しく解説していきます。
相続放棄ができない場合とは?
相続放棄ができないケースには、以下の3点が挙げられます。
①相続開始から3ヶ月を過ぎた場合
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に申し立てを行わなければならないため、この期間を過ぎると相続放棄はできません。
②相続財産の処分を行った場合
相続放棄をするためには、相続財産を一度でも処分したり管理したりしていないことが条件で、処分した場合は放棄できなくなります。
③成年後見人がついている場合
成年後見人がついている相続人は、単独で相続放棄を行うことができず、その判断に基づいて手続きを進める必要があります。

成年後見人制度についての詳細は、以下のコラムをご参照ください。
合わせて読みたいコラム
・後見人ができること・できないこと|誤解しやすい5つのポイント解説
財産(遺産)放棄との特徴の違い
財産(遺産)放棄は、相続人が遺産分割協議で特定の財産を放棄する意思表示をすることです。
相続放棄との大きな違いは、相続権そのものを放棄するのではなく、放棄する財産以外は引き継ぐことができる点です。
財産(遺産)放棄の特徴として、以下の4つが挙げられます。
①相続権は放棄しない
財産放棄では、特定の財産を放棄するだけで相続権そのものは失われず、他の遺産は引き継ぐことができます。
②家庭裁判所の手続きは不要
財産放棄は遺産分割協議での意思表示だけで済み、家庭裁判所での手続きは不要です。
③負債の免除はない
財産放棄では、放棄した財産に対する負債を免れることはできず、負債を免れたい場合は相続放棄を選ぶ必要があります。
④他の相続人との協議が必要
財産放棄を行うには、他の相続人との協議を経て、同意を得る必要があります。
相続について相談できるサイト
・相続税に特化したFP無料相談
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄は、故人の借金や保証債務を引き継がずに済む制度ですが、同時に遺産などのプラスの財産も受け取れなくなります。
次に、この章では、相続放棄のメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。
4つのメリット
相続放棄には、主に以下4つのメリットがあります。
①負債を引き継がない
相続放棄を選択すると、故人の借金や負債を引き継がずに済みます。
これにより、マイナスの財産を受け取らず、経済的な負担を避けることができます。
②相続トラブルを避けられる
相続放棄をすると、相続人としての権利を放棄するため、相続に関するトラブルから解放されます。
例えば、「遺産分割協議が進まない」「他の相続人と意見が合わない」といった問題に巻き込まれずに済みます。
③事業承継を円滑に行える
事業承継者以外の相続人が相続放棄をすることで、事業に必要な財産が事業承継者に集中します。
これにより、遺産分割協議を省略でき、事業資産がスムーズに事業承継者に引き継がれることが確実になります。
④法的負担を回避し、精神的負担も軽減できる
相続放棄をすることで、故人の負債に対する法的責任を免れるだけでなく、複雑な手続きや遺産分割に伴う精神的な負担を軽減することができます。
4つのデメリット
一方で相続放棄には、主に以下の4つのデメリットもあります。
①遺産を一切受け取れない
相続放棄をすると、故人の財産や遺産を一切受け取れません。
プラスの財産(例えば預金や不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払いの税金など)も含めて放棄するため、相続放棄を選択すると遺産を受け取る権利が失われます。
②後から撤回できない
相続放棄を行った後は原則として撤回することができません。
相続放棄の意思を示した時点でその決定は最終的なものであり、放棄した後に遺産を受け取ることはできません。
③他の相続人との関係が変わる可能性
相続放棄を行うことで、自分が相続人でなくなるため、遺産分割における権利を持たなくなります。
他の相続人との間で調整や意見交換ができなくなる可能性があり、後々関係がぎくしゃくすることがあります。
④相続放棄を選んだ場合、代襲相続が適用されない
相続放棄を選択した場合、その相続人に代わって子どもなどが代襲相続を行うことはありません。
代襲相続が適用されるのは、相続人が死亡している場合などであり、相続放棄を行った場合はその後に誰も相続人となりません。

代襲相続とは、相続人が亡くなった場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。
相続について相談できるサイト
・相続税に特化したFP無料相談
相続放棄の手続き方法
相続放棄を行う場合、相続が開始されたことを知った日から3ヵ月以内に手続きを行う必要があり、期限を過ぎると、相続放棄を行う権利を失ってしまうため、注意が必要です。
では最後に、その相続放棄の手続き方法について見ていきましょう。
相続放棄の申立て方法と必要書類
相続放棄の手続きは、主に以下6つのステップで進めることができます。
1. 相続開始の確認
相続放棄をするには、まず相続開始日を知ることが前提となります。
相続開始日は、通常、被相続人(故人)のご逝去日で、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
2. 家庭裁判所への申立て
相続放棄は家庭裁判所に申立てを行うことで成立します。
申立ての場所は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
3. 必要書類の提出
相続放棄を申立てる際には、以下の書類等が必要です。
・申立書(相続放棄を申請するための書類)
・戸籍謄本(相続人であることを証明するための書類)
・被相続人の死亡届受理証明書(死亡を証明するための書類)
・相続人全員の同意書(必要に応じて提出する書類)
参照サイト
・裁判所『相続の放棄の申述』
4. 家庭裁判所による審査
提出された書類をもとに、家庭裁判所が相続放棄の申立てを審査します。
申立てに問題がなければ、放棄が認められます。
5. 相続放棄の決定
家庭裁判所が相続放棄を認めると、「相続放棄の決定」が下されます。
この決定が下りると、正式に相続権が放棄され、相続財産(負債も含む)は一切引き継がれません。
6. 相続放棄の登記(任意)
相続放棄の決定を受けた後、相続放棄が登記されることがあります。
これは不動産を含む相続財産がある場合に重要となりますが、登記は必須ではありません。
相続放棄を行うための注意点
相続放棄を行う際の注意点として、以下3つが挙げられます。
①期限厳守
相続放棄の申立ては、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならず、期限を過ぎると認められなくなる点に注意が必要です。
②放棄後の責任
相続放棄後は、遺産の分割にも関与しなくなりますが、放棄を取り消すことは基本的にできません。
③代襲相続の対象外
相続放棄をした場合、放棄した人の子供(代襲相続人)がその分を引き継ぐことはありません。

相続放棄について気になることは、専門家を活用してみましょう。
まとめ
今回の記事のまとめです。
相続放棄は、故人の財産も負債も一切引き継がない手続きで、家庭裁判所への申立てが必要です。
これにより相続権がなくなり、借金の支払い義務も免除されます。
ただし、申立ては相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
財産放棄(遺産放棄)は、特定の財産を放棄する方法で、相続権は残ります。
家庭裁判所の手続きは不要ですが、負債の免除はない点に注意が必要です。